※星マークの評価ポイントは、星の数により、5点段階評価と3段階評価の2種類があり、合計点は最高で35点満点となります。
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 <HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX>
![これからお前は[すべて]を失う](gazou/harrypotter.jpg)
◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★★
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★★★★☆
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★★★★
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ★★★
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★☆
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★★★
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★★★
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★★★
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 33点
 <個人的感想>
<個人的感想>
とうとう、このシリーズもこれで5作目となりました。いやぁ、続きましたねぇ。ハリー・キャラハンのシリーズと並んでしまいましたよ。
しかも、これだけシリーズを重ねていながら、クオリティが全く落ちて無い所は凄いですね。3作目から、毎回監督を変えてきているのがいい方に転んでいるようです。映像や演出にそれぞれの特色のようなものが出ていて、同じシリーズながら、新鮮味があるんですよね。
今回、見たことも聞いた事もない人が監督に抜擢されましたが、「ドル箱シリーズの監督」という大役を見事に果たしたと思いますね。原作があるシリーズ物という事で制約もかなり多いでしょうし、毎回大ヒットを飛ばしているシリーズなので失敗したらエラい事になるというプレッシャーもデカいでしょう。そして、そんな中で自分の色を出しつつ監督をする、というのは相当大変な仕事じゃないかと思うんですよね。
私にとっては、「低予算のインディーズ映画界で名をはせている監督」とか「自分の撮りたい映画を自分の撮りたいように撮っている巨匠監督」よりもよっぽど凄い仕事をしてると思えてしまいます(映画を芸術と捕らえてないからそう思うんでしょうね)。
で、今回の『不死鳥の騎士団』ですが、雰囲気は3作目の『アズカバンの囚人』と似てましたね。シリーズ中、『アズカバン』にしか出ていなかったキャラや場所が今回再登場しているという事もありますし、ハリーの内面の描写や葛藤をメインに描くという内容も似ています。
『アズカバン』はシリーズ中で個人的に一番面白くなかった映画だったので、今回の『不死鳥〜』も期待ほどには楽しめなかった可能性もあったんですが、5作目に臨む前に「3作目がイマイチだった」というのを、レンタルで再見してしっかり解消してきていたので、きちんと、期待通りに楽しむ事が出来ました。
ただ、てっきり、前作で復活したヴォルデモートとの戦いが前面に出てくるのかと思っていたんですが、まだその段階じゃなかったんですね。話が佳境に入ってる雰囲気があるのに、ストーリーは一向に前に進まない、みたいなもどかしさがちょっとだけありました。
しかも、「これから盛り上がっていきそうだな」という展開になった所で終わるんですよね。2時間半近くある大作を見終わった後にも関わらず、「え、これだけ?もう終わり?」とか思ってしまいましたよ。それだけ、長さが気にならない内容だったという事でもあるんですけど。
まあでも、よくよく考えたら、今までのシリーズと構成自体は変わってないんですよね。「ハリーとヴォルデモートの因縁」にまつわる、シリーズを通してのエピソードの合間に、シリーズのその回だけで完結するエピソードが挟まれる、という感じで。
で、今回の完結エピソードは、「ホグワーツにムカつくおばちゃん先生が来て、全てが引っ掻き回される」というものです。で、このおばちゃん先生が、まあムカツクんですよ。同じことを2回書いてしまうぐらいムカつきましたね、ええ。
要するに、規律や秩序を重んじる、頭でっかちのクソティーチャーなわけですが、「ソイツの横暴なやり方」「それに反発する生徒」という、学園ドラマの1エピソードみたいな展開を見せてきます。
前作が「3大魔法学校対抗試合」という、アクション性の高いエピソードだったせいか、何だか一気に地味になってしまったような気がしてしまいました。まあ、基本は魔法学校が舞台の学園物という体裁の映画なんですし、これはこれでいいんですけど、やっぱり、あのおばちゃんがムカついて、見てるのに苦痛を伴いましたねぇ。「こいつ早く死なねぇかな」とか思ってしまいましたよ。
一方の、シリーズ通しのエピソードとも言えるパートでは、ハリーがダークサイドに落ちかけるという、流行の展開を見せてきました。まあ何しろ、この若さでかなりの重みを背負っている立場ですからね。さらに魔法省から裏切られ、クラスメイトから嘘つき扱いされと、もう心労重なりまくりな状態です。そこに、あろうことか、ヴォルデモートが「精神乗っ取り」的な技を使って来るんですよ。もう、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ終盤のフロドみたいな状態になってましたからね。いつハリーが「指輪は俺のものだ」と言い出すんじゃないかとハラハラしましたよ。
ただ、同時に、今回はハリーの成長というのが最も見て取れるストーリーでもあるんですよね。「ハリーがこの局面でどうするか」というのが見てて面白いですし、緊張感がありましたね。
映像面では前作に比べて圧倒的に地味になったんですが、クライマックスのバトルはシリーズ最高の大迫力シーンでした。今まで見た事も無いないほどのスピードで攻撃が繰り出される魔法合戦には、口あんぐりでしたね。
不死鳥の騎士団のメンバーと、ヴォルデモート配下のデスイーター軍団の対決が始まるんですが、もう、こいつらが、ハリー率いる自警団「ダンブルドア軍団」とはレベルそのものが違う戦いっぷりを見せるんですよ。
これまで、魔法はみんな単発で放ってましたけど、こいつらはもう連射しちゃってるんですよね。まさにハイレベルです。もしかしたら、同時に防御とか回避の魔法も使ってるんじゃないだろうか。
で、そのハイレベルな戦いの中に、ハリーが参加してるというのが驚きです。これまで、「主役なのに、強いんだか強くないんだか分からない」という微妙な戦闘力だったハリーですが、やはり、同級生の魔法使いからは思いっきり抜きん出ている存在だった事が分かりましたね。やっぱり、主人公はこうでなくては。
今回で魔法使いとしても主人公としても大きく成長を遂げたハリーの、次回作での活躍が今から楽しみでしょうがないです。どうも今回、腹八分目な感じの内容だったせいか、今まで以上に「見終わった後の、次回作が楽しみ度」が高かったですね。でも、次はいつになるんだ(来年の年末ですかね)。
アドレナリン <CRANK>

◎満足度 ★★★☆☆
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★☆☆☆
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★★★★☆
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★★☆☆
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ★★☆
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★☆
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★★☆
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★★☆
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★★☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 22点
 <個人的感想>
<個人的感想>
中国製の怪しい毒を打たれて余命1時間ばかりとなった主人公のヒットマンが、「アドレナリンを出せば毒が回るのを遅らせる事が出来る」という事で無茶をしまくるという、言ってみれば一発ネタの映画です。
「まるでB級映画みたいなネタだな」と思ったら、その中身も本当にB級映画そのものといった感じでした(それも、未公開系の・笑)。何ともバカバカしい展開の連続で、悪い冗談を見てるかと思う事もしばしばでした(笑)。「普通のアクション映画」かと思ってみたらエラい目に遭う、そんな感じの映画ですね。
ですが、その展開のアホっぽさはもちろん狙って出してるものです。主人公の無茶な行動の数々に笑い、そして呆れる、というのが正しい鑑賞法なんでしょう。しかもこの人、「アドレナリンを出さなきゃいけない」というのを知る前から無茶な行動を見せてましたからね(笑)。
主人公の行動だけでなく、演出自体もかなりハイテンションで、見てるだけで疲れるぐらいです。
その演出面は、全体的に『スモーキン・エース』と似たような雰囲気があるような気がしました。でも、似てるんですけど、あちらに感じられた“クールな雰囲気”はあんまり無いんですよね。主人公が無茶な行動をしまくる内容なせいなのか。
それに、結構下品なんですよね(笑)。ジェイソン・ステイサムが尻をチラチラさせながら街中を疾走したと思ったら、「これは何のAVだ」と思うような変態プレイも登場する始末。でも、こうでもしてアドレナリンを出さないと死んでしまうんだからしょうがない。
こういうのを凝った映像で見させられても、“クール”よりも“何だこれ?”と思うだけです。でも、当然これも計算の内なんでしょうな。
ラストも、観客をおちょくってるかのようなふざけたもので、とてもじゃないけど人に勧める事の出来ない映画です。正直、私もそんなに好きなタイプの映画じゃないんですけど(爆)、「たまにはこういうふざけた映画もいいな」とは思いましたね。
それにしても、よくこんな狂った映画を作る気になったものだと思いますね。ジェイソン・ステイサムもよく主演を引き受けたものです。今回の仕事は間違いなく人に誇れるものじゃないですからね(笑)。
そして、そういう仕事を敢えて引き受けた辺りに、ステイサムの漢を感じますねぇ。
アポカリプト <APOCALYPTO>

◎満足度 ★★★★☆
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★☆
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★★★★☆
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★☆☆☆
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ★★★
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★☆
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★★☆
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★☆☆
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★★☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 24点
 <個人的感想>
<個人的感想>
『300』に続き、半裸の男達がスクリーンを埋め尽くす映画が出てきました。しかも、こちらはケツも出してます。肉体美では『300』劣るものの、セクシーさでは負けていません。
とは言え、実はこの映画、男のケツが見どころの映画ではないんです。マヤ文明を舞台に、“マンハント”から逃走し、家族の元に帰り着こうとする男のジャングルサバイバルアクションの映画なのです。
見る前は、単にマヤ文明を描いた歴史物映画なのかと思っていて、正直、見に行こうかどうしようか迷っていました。何しろ、残酷な文明だという話を聞いていたうえに、監督は残酷描写大好きのメル・ギブソンです。きっと、映像的にかなりキツい事になっているんだろうなと。まあ、平常時の私なら特に迷いもなく見に行ったと思いますが、最近夏バテ気味なのか、映画を見に町まで出掛けるのも一苦労なぐらい体力が低下してるんですよね。
ですが、まるで『ランボー』のようなジャングルアクションが出てくると聞いて、頑張って見に行ってみたんです。しかし、アクションシーンが始まるのが後半からで、それまでがもう長い事長い事。この「後半になってようやく展開がスピーディになる」というのは、『ゾディアック』と同じような流れでしたね。
前半の平和な時のシーンとか、中盤の過酷な連行〜残酷な儀式シーンとかも、それぞれ見どころがあって退屈するという事はなかったんですが、やっぱり、「アクションシーン目当て」で見に来たのがいけなかったのか、「展開遅いな」と思ってしまいました。
でも、マヤ文明の時代を見事に作り上げて見せた映像は凄かったですね。こういう、きっちりと作品世界が作り上げられてる様は、見てて“大作感”が感じられていいです(大作映画好きにとっては)。
で、目当てである後半のアクションシーンですが、噂通りに凄い迫力でした。
傷を負いながらも疾走する主人公に、怒人の形相で追いかけて来る土人。ジャングルの中、全力疾走での追いかけっこをスピード感満点の映像で見せてくれます。これが下手な監督だったら、「カメラを揺らせて臨場感を出しました!」みたいな勘違い映像を出して観客を酔わせていた事でしょうね(まあ、一番後ろの席で見てたから気付かなかっただけで、もしかしたらある程度は揺れてたのかも分からないんですが・笑)。
そして、勝手知ったる地元の森に逃げ帰った後の、地の利を活かして反撃に転ずるクライマックス!もう、後半はほんと『ランボー』を思い出すような見事なアクションぶりでしたねぇ。いやぁ、満足でした。
それにしても、マヤ人というのは、ほんと残酷ですねぇ。心臓を取り出したり、首を切り落としたり。しかも、その首をピラミッドの上から転げ落として、それを下でキャッチする係がいたりするんですよ(素手で捕るわけじゃなくて、網でキャッチするんですが)。
逃げる主人公を追いかける連中の中には「奴の皮を剥いで、目の前でその皮をまとってやる」なんて事を言い出す奴も出る始末ですし。このあまりに大胆な発想には、猟奇殺人鬼も裸足で逃げ出す事でしょう。
さらに恐ろしいのは、この「いけにえの腹割き&首切りショー」を大勢の民衆が大喜びで見物してる事ですね。何なんだコイツらは。この野蛮人共め。
でも、これが当時のマヤ人の娯楽みたいなものだったんでしょうね。で、今娯楽として人が死にまくる映画を見てる我々と一体何が違うんだろうとか思ってしまいました。まあ、「実際に人を殺してる映像を見て喜んでるわけではない」という違いはありますけど。でも、生首が階段をコロコロと転げ落ちる映像を見て、不謹慎ながらも笑ってしまった私も、このマヤの民衆と大差無い野蛮人なのかもしれないですね。ならば、「誰にも被害や迷惑をかけない野蛮人」という自覚を持って、今後も人が死にまくる映画を喜んで見ていく事にしますか。
ダイ・ハード4.0 <LIVE FREE OR DIE HARD>

◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★★
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★★★★☆
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★★★☆
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ★★☆
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★☆
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★★★
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★★★
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★★★
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 31点
 <個人的感想>
<個人的感想>
ついに登場した、全世界待望の『ダイハード』第4弾です。
で、見終わって真っ先に思ったのが、「マクレーン、死なねぇなぁ〜」という事でした。これは呆れて言ってるのではなく、感嘆しているのです(笑)。
マクレーンを襲う危機のデンジャラス度がシリーズ最高ぐらいのものになっていて、もう、銃弾は飛び交うは、車は飛び交うは、カンフー使いに襲われるはのエラい騒ぎです。しかもその攻撃の激しさゆえ、マクレーンのいた建物が瓦礫の山になる事もしばしばなんですが、それでも死なないんですよ、この男は。
凄いのは、それを「余裕で切り抜けている」という感じがない所ですね。もちろん、マクレーンは強くてマッチョなヒーローなんですけど、「死なないように必死に頑張っている」みたいな面が感じられるんですよね。
危機的状況を切り抜けられるのは見る前から分かってるんですけど、でも、見てて「これはヤバいのでは!」なんて事を思ってしまうんです。
もちろん、演じるブルース・ウィリスの雰囲気というのもあるんでしょうけど、何よりも、設定上、マクレーンに必要以上の戦闘的能力が与えられてないというのも大きいと思いますね。例えば、元特殊部隊だとか、超絶なカンフーを使えるとか、凄腕のスパイの訓練を受けているだとか。
そういうのが無い、設定上はただタフなオヤジみたいな奴が、あれだけの壮絶な修羅場をくぐって行く、という辺りが面白いんですよね。まあ、「高い所から落ちてもあんまりダメージが無い」という常人とはかけ離れた頑丈さを持っていたりするんですが、これはマクレーンに限った事ではないですからね、このシリーズの場合(『3』ではサミュLのとっつぁんも相当高い所から落ちたのにダメージほとんど無しでしたし・笑)。
アクション面に関してはシリーズ中でも相当力が入ってて見応えがあったんですが、一方、ストーリー面に関しては、ほとんど凝った所の見られない、「普通のアクション映画のストーリー」みたいな感じだったのはちょいと残念でしたね。
敵の見事な計画をマクレーンが暴く、というのがこれまでのシリーズのストーリーの良い点の一つだったんですが、今回のマクレーンはほとんど頭を使う機会が無かったような感じでしたからね。何しろ、相手がデジタルな連中なので、アナログなマクレーンは完全に置いてきぼりなわけですよ。
見る前は、アナログなマクレーンがデジタルな敵軍団にどう立ち向かうのかという辺りにもっと面白味のあるストーリーなのかと思ってたんですが、実際にマクレーンと現場でやり合うのは、ハイテク機器ではなく銃火器を装備した武装集団でしたからね(あと、カンフー使いもいたか・笑)。
一応、アクション大作としては文句無い傑作なんですけど、『ダイハード』の新作としては、やはり思い入れのあるシリーズだけに、こんな程度でまとまってしまったのは残念でしたね。
まあ、こういう内容として作られてしまった以上、「もっと脚本に凝って欲しかった」みたいな泣き言をほざいていても仕方がありません。これはこれとして認めていかなくてはなりますまい。
まず、こういう「爆破と銃弾の雨あられの中、マッチョヒーローが大暴れ!」みたいな単純なアクション大作を最近とんと見て無かった気がするので、そういうのが好きな私みたいな人間にとっては、まさに貴重な一作です。
あと、話のスケールのデカさも実に魅力的でしたね。建物内でのドンパチだけでなく、市街でのパニックの様子もちゃんと出てきてくれて、普通のアクション大作映画以上の大作感というのが感じられたものでした。こういう、刑事アクションの範疇で収まらない大事件が出て来るのがこのシリーズのいい所ですからね。
だいたい、刑事が戦闘機に襲われるなんて事態、滅多にない事ですよ(滅多にどころじゃない・笑)。でも、こんな有り得ないアクションシーンに、“アクション映画的説得力”を付けて見せてくれる所がハリウッドのアクション大作の素晴らしい所です。
アクションシーンも、ただ金を掛けて派手にしたというだけじゃなくて、ちゃんと映像的に凝ったものになってるんですよね。それこそ、「こんなアクションシーン、今まで見た事も無い!」と思うようなのが出てきたりするんです。
例えば、上空のヘリから銃撃され、パトカーで逃げるマクレーンがいかにして反撃するのかとか、こっちに向かって車が吹っ飛んで来た時、何が原因で助かるのかとか。
嬉しいのは、そういう「見た事の無いシーン」が、いわゆる“CGバリバリ”なシーンじゃないという点ですね。いや、もちろん特撮は使ってますけど、“CGっぽさ”を感じさせない画作りになってるんです。
『マトリックス』シリーズや『スパイダーマン』シリーズみたいな、CGを目一杯使ったデジタルなアクションシーンも好きですけど、やっぱり、90年代のアクション映画をリアルタイムで見て育った世代としては、こういう雰囲気のアクションシーンの方が見てて燃えますね(映画ファンになるのがもっと早かったら、これでも「CG使い過ぎ」と思ったのかもしれませんけどね)。
ゾディアック <ZODIAC>
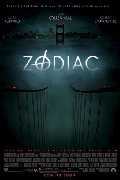
◎満足度 ★★★★☆
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★☆
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★★★☆☆
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★☆☆☆
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ★★☆
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★☆
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★★☆
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★☆☆
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★★★
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 23点
 <個人的感想>
<個人的感想>
事件発生から40年近く経っていながら、いまだに未解決である「ゾディアック事件」が、あの『セブン』のデビッド・フィンチャー監督によって映画化されました。
で、また『セブン』みたいなイカしたサイコ・サスペンスになってるかと思ったら、これがまた、エラく地味なサスペンス映画でした。
まず、オープニングクレジットからして何も凝った所の無いものでしたし、その後の展開も実に淡々としたものでした。
特に「主人公」という存在も決められてないみたいで、事件を誰かの目線で追う、というものでもなく、ただ当時の状況を一歩引いた所から映しているだけ、というような感じなんです。
そんな地味な展開が2時間近く続き、後半からようやく、ジェイク・ギレンホール演じる風刺漫画家が主役となって、真剣に事件を追うという展開になっていきます。
前半戦は正直退屈だったんですが、この後半戦からはストーリー展開のテンポも早くなって、俄然面白くなってくるんですよね。
その、ギレンホールが調査を開始する時点で、すでに劇中では事件発生からかなりの年月が経っているという状況です。
それを見ていて、こういう、忘れ去られそうになってる事件を追ってくれる人が出たというのは、遺族にとっては心強いだろうな、なんて事を思ったのですが、この映画、犠牲者とか遺族に関する描写が全然無いんですよね。
この、淡々と事件のみを追うという手法や、映像派の監督なのに、まるで凝った描写が無いという辺りに、どこか引っ掛かる物を感じてしまいましたね。ちょっと冷たいと言うか何と言うか。
ですが、何しろ監督はあのフィンチャーですからね。今までになく地味な演出になっているのにもきっと何か意味があるのに違いありません。とは思うものの、結局私にはフィンチャーの意図する所は分かりませんでした(爆)。
でも、見終わった後に私の中にある変化が起こっていたんです。それは、劇中でゾディアック事件に嵌まってしまった人々に見られたような、「事件に対する興味」というのが、何か異常に出て来てしまったんですよね。なので、700円もするプログラムを買ってしまいましたし、その後本屋に直行して原作本も買ってしまいました。何故か、この事件のことをもっと知りたくてたまらなくなってしまったんです。
で、これはもしかしたら、フィンチャーの術中にまんまとはまってしまったのではないのかと思うんですよ。あの地味に見えていた展開が実は全て計算され尽くした演出で、私の深層心理にしっかりと「事件に対する興味」の根を植え付けていたのではないのだろうか。考え過ぎですか。
それにしても、面白い事件なんですよね。現実に人が殺されている事件で面白いというのもどうかと思うんですが。
まず、私はゾディアックという犯人の事を、てっきり、切り裂きジャックとか、あるいは後のアメリカを騒がせたシリアル・キラー達みたいな、超凶悪で残忍なサイコだと思っていたんですが、その殺しの手口は「銃で撃つ」とか「ナイフで刺す」といった、実にオーソドックスな手口なんですよね。殺した後に犠牲者を解体するとか、そういう猟奇的な事をしてないんです。
また、最終的に殺したとされる人数も、確か5人ぐらいなんですよね。「それだけ?」みたいな。いや、殺される人は少ないに越した事はもちろんないんですけど、「有名なサイコキラー」の水準からすると、相当少ないですよね。
もしこの事件が未解決じゃなかったら、果たしてここまで後々までに騒がれるような事件だったのだろうかとも思ってしまいます。でも、生憎と捕まってないうえに、コイツが新聞社に送り付けた暗号文の中に、未だに解かれていない暗号もあったりするという事から、こんなに後世まで人々の関心を引き付けているんでしょうね。何しろ、「警察や新聞社に挑戦状を送り付ける」という、いわゆる“劇場型犯罪”というものの草分けだったようですし。
それに、あまり残虐じゃないというところも、完全にイカれたサイコとはまた違う、「謎の殺人者」という感じがあって、このゾディアックという存在を、より興味深いものにしているのかもしれませんね。
でも、何で捕まえられなかったんでしょうかねぇ。どうも、そんなに周到な計画を練ったうえでの犯行というわけでもなかったみたいなのに、刑事や新聞記者が追っても全然尻尾を掴ませないんですよね。
見ていて、「当時にCSIがあれば一ヶ月程で逮捕出来たに違いない」とか思ったんですが、最有力容疑者が、犯人の指紋や筆跡と当てはまらなかったりするんですよね。
時折、思いっきり姿を見られてたり、手書きの手紙を送りつけたりと、犯人に近づけそうなヒントが結構あるし、色々と調べていくと、犯人に近づけそうな手がかりとかが発掘出来たりするんですよね。でも、真相までには至らないんです。まるでイタチごっこみたいな状況ですね。
これだけ手がかりがあって、何で逮捕出来ないのか、というのも、この事件に興味を惹かれる一因かもしれないですねぇ。何か、あと一歩でどうにかなりそうな雰囲気もあるんですよね。
 ←前に戻る
←前に戻る
![これからお前は[すべて]を失う](gazou/harrypotter.jpg) ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>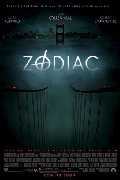 ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ←前に戻る
←前に戻る