※星マークの評価ポイントは、星の数により、5点段階評価と3段階評価の2種類があり、合計点は最高で35点満点となります。
ボーン・アルティメイタム <THE BOURNE ULTIMATUM>
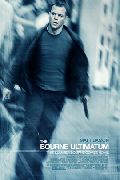
◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★★
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★★★★★
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★★★★
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ★★★
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★★
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★★★
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★★★
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★★★
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 35点
 <個人的感想>
<個人的感想>
いやぁ、凄い映画でしたねぇ。何なんでしょう、この迫力とテンションの高さは。シリーズ中、最もアクション度が高かったですね。最近批評家受けするタイプの映画を選ぶ事の多いマット・デイモンが主演してる映画なんで、前作より派手になることはまず無いと思ってましたからね。これは驚きました。
映画の約半分はアクションシーンなんですが、それも誰かを追っていたりとか、何かに追われていたりといった、緊張感の高いサスペンス要素の含まれたアクションです。そして、シリーズお馴染み、ボーンの“プロの技”が如何無く発揮されていきます。
肉体アクションとはまた違う、“知的アクション”といった趣ですね。『ダイハード4』のアクションとは全く別種の物ですが、同じぐらいハイレベルのアクションシーンであるという事は確実に言えますね。
そして、そういうアクションを全く違和感なくやりこなしたマット・デイモンのセンスは素晴らしいです。ほんと、才能のある人なんですねぇ。ここまでやられるともう感心するしかないですね。
で、このアクションシーンにおいて、前作もそうだったんですが、画面がかな~り揺れるんです。例の「手持ちカメラによる映像で臨場感を出そうとする」系の演出ですよ。
そして格闘シーンにおいては、揺れるわカット割りは早いわで、何が起こってるのかがほとんど分からないぐらいです。
本来なら、こんな見辛いアクションシーンを出されたらイライラする所ですけど、この映画では全て、本当に臨場感が出てるんですよ。相当揺れてたと思うんですけど、『キングダム』みたいに酔う事もありませんでしたからね。なるほど、「カメラを揺らして臨場感を出す」というのは不可能な事ではなかったんですね(でも、スクリーンに近い座席で見たらキツかったかもしれないし、そうそうマネ出来る技術でもないいと思うんで、他の監督はどうか見習わないで頂きたい)。
あと格闘シーンですけど、これがもう、本当に凄いんです。ここまで凄まじい対決シーン、ここ数年はお目にかかっていませんでしたね。確かに、何が起こってるのか、見ててほとんど分からないんです。でも「目で追えないほどのスピードの格闘が繰り広げられてる」というのが伝わってくるんです。超人のバトルの映像化とでも言うんでしょうか。この猛烈なまでの迫力にはたまげましたね。興奮させてもらいました。
前作と監督も同じなら、音楽も同じだし(担当が同じ人というだけでなく、曲自体がほぼ一緒)、登場人物も結構被ってる。そして最後はカーチェイスと、もう、内容自体は前作の焼き直しともとれるぐらいなんですけど、前作とも一作目とも違う『アルティメイタム』ならではの面白さがちゃんとあるんですよね。シリーズ全てに一貫した雰囲気やカラーというものがあり、尚且つ、それぞれ違った面白さがあるという、これがシリーズ物映画の理想形なんじゃないだろうか(1話完結型のシリーズにしろ、連続ストーリーのシリーズにしろ)。
この映画は“連続ストーリー”タイプの続編で、前作のクライマックスからそのまま話が続いていく、という手法を使ってきました。ですが、前作のクライマックスから今作に移り、そこから1時間以上進んだところで、前作のラストシーンに繋がる、というのは初めて見ましたね。これはかなり新鮮でした。前作のラストシーンの前にはあれだけ色々なことがあったのか。
その前作のラストシーンもかなりクールでしたが、今回のラストシーンも実に良かったですね。「まさか、ここに繋げてくるとは!」と感動するような映像で。
あと、シリーズを通して、エンディングテーマが絶妙なタイミングで鳴らされてきましたが、今回も、それは見事なタイミングで鳴らしてきました。イントロが流れ出した瞬間「来た!」とか思ってしまいましたよ。しかも、流れるテーマ曲が、前2作と違って「アルティメイタム仕様」の新バージョンです。フィナーレに相応しいエンディングテーマでした。
ラストシーンの映像と、このエンディングテーマから「これでジェイソン・ボーンの旅も終わりなんだな」という思いがこみ上げてきて、非常に感慨深いものがありましたね。
そうそう、今回、歌詞の字幕がついたのは嬉しかったですね。ああいう歌詞の歌だったんですね。この映画の為に作られた曲じゃないですが、結構、内容に合ってる歌だったんですね。
スターダスト <STARDUST>

◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★☆
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★★★★★
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★★☆☆
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ★★★
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★★
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★★★
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★★☆
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★★★
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 31点
 <個人的感想>
<個人的感想>
ファンタジー映画というジャンルももはや供給過剰気味で、予告編を最初に見た時は「ああ、またお馴染みのジャンルの映画が一本増えたのか」と思っていたのですが、見てみたら、結構、他の同ジャンルの映画とは差別化の計られた、むしろ新鮮味すら感じられる映画でした。
何が違うのかと言うと、ストーリー展開とか登場キャラクターの会話とかが軽いんです。ストーリーは単純で平和で甘ったるいものですし、各登場人物のキャラクターも、マンガみたいな分かりやすさがありました。そのうえ、軽くコメディっぽい演出も入り込んでいて、映画全体にライトな感覚があるんですよね。
多分、中高生向けのライトノベルだとかアニメなんかではこういう雰囲気のファンタジーは腐るほどありそうな気がするんですが、映画ではあまり見ないタイプのような気がします。
かと言って、若者とかオタク向けかと言うとそうでもなく、誰が見ても楽しめるような、広い層にアピール出来るような完成度の高さが感じられるんです。最近の映画では『トランスフォーマー』の精神に近いものがあるんじゃないだろうか。
軽い感じの雰囲気がある事から、他のファンタジー大作にある“壮大さ”はほとんど無いんですけど、映像には大作感はしっかり感じられるんです。変なB級っぽさも無く、しっかり作りこまれた映画という印象で、普段重い映画を好んで見てるような人でも「意外に楽しかったな」と好印象を持ってもらえるのではないかと思います。
この映画の世界観は、『ロード・オブ・ザ・リング』のような、完全な異世界の話ではなく、現実の世界と壁を隔てた隣にファンダシーワールドが存在している、というものです。「ワードローブの中にファンタジーワールドへの入り口があった」という『ナルニア国物語』に近い雰囲気でしょうかね。
ですが、その「二つの世界を隔てる壁」というのが、家の塀より低いぐらいのものですし、しかも一ヶ所崩れてる所があって、もう、誰でも自由自在に行き来が出来るんです(一応、カンフーを使う謎の老人が番をしてるんですが)。
普通の映画だったら、こんなに簡単に異世界に行き来できる場所があったらエラい事なんですけど(現実的に考えて、大騒動が起こる事必至ですからね)、何故か、この映画では主人公以外の人は壁の向こうに行こうとも思わないようなんです。
もはやご都合主義的ですらあるんですが、映画全体から、そういうのが許される雰囲気というのが漂ってるんですよね。暗黙のルールみたいな感じで。
そもそも、ヒロインが“星”というのも何だかよく分からない設定で、私も最初の頃はちょっと違和感がありました。ヒロインが「私は星よ」と言い張り、主人公は「君は星なのか」と納得する会話は、頭のおかしい人同士のやりとりとしか思えません。
でも、見ているうちに自然に「クレア・デインズは星だ」と思ってしまえるんですよね。まさに、魔法にでもかかったみたいでした。
で、この人は星なので、時々体が光り輝いたりするんです。どうも、幸せな気分になると光るらしいです。で、ストーリーが進むにつれて主人公と恋仲になり、ついには2人で話してるだけで光ったりするんです。
いやぁ、甘いですなぁ。あまりにも甘すぎて、もう、見てるだけで糖分の取り過ぎになりそうですよ。こんな演出を下手な恋愛映画でやられたらウンザリすると思うんですが、この映画では、ただ微笑ましい描写に思えてしまうんです。きっと、もうこの時点でこの映画の雰囲気に完全に馴染んでしまっていたからなんでしょうね。
各登場人物も、それぞれしっかりキャラクターが立っていましたね。まず、主人公があまり頼りにならないボンクラ青年というのも面白い所でした。後半になると段々と頼もしくなってくるんですが、途中まではほんと、とても物語の主人公がやるとは思えないような失敗を当たり前のようにしでかす奴でしたからね。
大御所、ミシェル・ファイファーの絵に描いたような悪い魔女っぷり(でも、一昔前のコミックヒーロー物の悪役みたいな大袈裟な演技は無し)や、デ・ニーロの海賊のキャラクターもユニークで実に良かったです。特に、このデ・ニーロのキャラは、この映画のみならず、最近の映画全般で考えても、相当印象的なキャラクターでしたね。
あと、悪い王子兄弟も面白い連中でしたね。王の座を巡って争うんですけど、死ぬと仲良くゴーストになって、残りの兄弟の行動を観戦して楽しんだりしてるんです。もう、驚く程の平和さですよ。
ラストも「100%ハッピーエンド!」という、ある意味気合の入ったものでしたし、エンドクレジットの曲も笑えましたし(普通のクラシックの曲なんですけど、劇中でとんどもないシーンで使われていたので・笑)、見終わった後に幸せな気分になれるような映画でした。こういう映画は大好きですね。特に、前に見たファンタジー映画が『パンズ・ラビリンス』だったせいか、余計にこの映画の明るさ、平和さが有難く思えたものでした。
バイオハザードⅢ <RESIDENT EVIL: EXTINCTION>
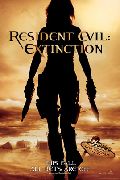
◎満足度 ★★★★☆
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★☆
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★★★☆☆
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★★☆☆
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ★★☆
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★☆
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★★☆
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★★★
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★★★
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 26点
 <個人的感想>
<個人的感想>
ウイルスが蔓延し、砂漠化した地球が舞台、という、ついにゲームから完全に離れた内容になってしまいました。と言っても、元々私はこのシリーズに原作ゲームの雰囲気を微塵も感じていなかったので(舞台やストーリー等に共通する要素はあるんですが)、まあ、いいんじゃないでしょうか。でも、原作ゲームをやってる時の感動が蘇ってくるような映画版も見てみたかったものです。
ストーリーはゲームから離れましたが、まだ多少の「ゲームの面影を残す点」は存在します。登場キャラクターにクレアとウェスカーが出てきた事と、“追跡者の第2形態”が出てきた、という点です。追跡者はゲームでは結構苦しめられたんですが、そんな化け物と主人公アリスが接近戦で互角に戦う姿は、何だかんだで、中々爽快でした。
クレアは、前作のジルと違って衣装がゲームのままじゃないんで「たまたま同じ名前のキャラ」みたいな感じでしたが(思えば、カルロスもそのタイプか)、ウェスカーはしっかりとグラサンを装備していて笑ってしまいました。しかも、今頃になって登場するとは思ってなかったんで、初登場シーンを見た時は「うわっ、出た!」と呟きそうになってしまいましたよ。
さて。今回、ゲームから離れた代わりに、ゾンビ映画により近づいたような感じがありました。「他のゾンビ映画で見た事あるシーン」が結構出てきましたからね。特に『死霊のえじき』の模倣に近いシーンや、『ドーン・オブ・ザ・デッド』そっくりな場面など、「もうちょっと似ないように工夫出来なかったんだろうか」と思うぐらいのリスペクトっぷりです(鳥ゾンビは、やっぱりヒッチコックの『鳥』からとったんでしょうね。まさか『サンゲリア2』からとったんじゃないですよね・笑)。
こういったお馴染みの場面が出てくる事で、ゾンビ映画ファンとしては今までのシリーズよりも楽しめたという面もあるんですが、新鮮味がまるで無い辺りにはちょっと引っかかるものがあって、素直に「シリーズ最高傑作!」とは言えないもどかしさがありましたね。
ただ、シリーズ3作、全て監督が変わりましたが、どうやら、今回のラッセル・マルケイが一番いい腕をしていたように思えました。何がいいって、アクション演出にキレがあるんですよね。
一作目はゾンビの動きにほとんどやる気が感じられませんでしたし、『Ⅱ』では流行の「画面揺らし&早いカット割り」で、アクションシーンがほとんど見えない状態でした。と言うわけで、アクション・ホラーなのに、アクション面に問題を抱えていたというシリーズだったんですが、ここにきてようやくまともなアクション演出を得る事が出来たようです(すると、やっぱり『Ⅲ』が一番良かった、という事になるのか)。
中でも、超人と化したアリスが、『ドーン・オブ・ザ・デッド』そのままな感じの、全力疾走で襲ってくるスーパーゾンビ軍団と対決するシーンは燃えましたね。『ドーン~』では、登場人物にとってかなりの脅威を誇っていた全力ゾンビーズですが(『バイオⅢ』でも、アリス以外の登場人物にとっては最悪の脅威でしたし)、そんな輩を接近戦で葬っていく姿には、単純に「凄ぇ!」と思ってしまいます。
他にも、所々に「おおっ!」と思うショットが出てきたりしますし(カルロスがタバコを吸うシーンとか)、ラッセル・マルケイ監督の「オレはまだ死んでないぜ!」という気合が感じられるようでした。
ちなみに、この映画の「舞台が砂漠」という辺りから、『マッドマックス2』を連想する映画ファンが大量に出たようなんですが、私だけですかね、この映画を見て『レイザーバック』を連想したのは(笑)。あの映画は砂漠じゃなくて荒野が舞台だったと思うんですが、何か分からないですけど、「もしかしたら、ブタちゃん達も出てくるのでは!」なんて変な期待感も湧き上がる始末でしたよ。
で、「何でこんな映画が思い浮かんだんだろう」と思ったんですが、実は監督が同じだったんですよね。もしかしたら、砂漠の映し方に『レイザーバック』を連想させるようなショットが入り込んでいたのかもしれませんね。
沈黙のステルス <FLIGHT OF FURY>
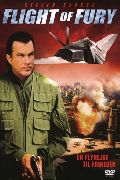
◎満足度 ★★★☆☆
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★☆☆☆
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★★★☆☆
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★★☆☆
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ☆☆☆
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★☆
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★☆☆
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★☆☆
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★★☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 17点
 <個人的感想>
<個人的感想>
まあ、つまらない映画でした。
何かもう、この映画について特に語る事も無いんですけど、感想が1,2行で終わりというのもなんなのでどうにか頑張ってみますか。
とりあえず言えるのは、セガール・ブランドの映画の質の低下がここ数年、止まる事を知らない状況になてしまっている、という事でしょうか。
セガール大先生自身のやる気の問題もありますが、その前に、監督が酷いんですよね。前の『沈黙の奪還』のミヒャエル・ケウシュが今作も監督ですが、多分、この人には面白い映画を撮る能力が無いんだと思います。『撃鉄』『沈黙の標的』のマイケル・オブロウィッツといい、セガールは才能の無い監督を引っ張り出してくるのが得意らしいですね(ただ、ミヒャエルの前では、オブロウィッツも、『DENGEKI』のバートコウィアクも、名匠に思えてきます)。
そんな中、この映画の「良かった点」を辛うじて挙げてみるなら、クライマックスの一連のアクションシーンに多少の見応えがあったという事ですかね。
敵の基地に攻め入ったセガールですが、目標であるステルス機のある格納庫内では銃が使えない(ステルスに当たるとマズいから)という理由で、主にナイフを使ったバトルが繰り広げられる事となり、お待ちかねのマーシャルアーツ・アクションが見られるわけです。
まあ、例によって「揺れるカメラ」「細かいカット割り」などでよく見えないアクションにはされてるんですが、それでも、「セガールが、次々に現れるザコを次々瞬殺している」というのはどうにか伝わってきたので、セガールの相変わらずの無敵っぷりを楽しめるシーンではありました。
また、その後に出てくる、セガールの乗るステルスと敵のF-16戦闘機との空中戦も、まあ迫力がありました。『トップガン』のドッグファイトシーンを水で薄めたような貧乏臭い映像でしたけど、「セガールが戦闘機に乗って戦っている!」というのは、『インデペンデンス・デイ』の「合衆国大統領が戦闘機に乗って戦っている!」というのに通じる楽しさがありましたね。
ブレイブ ワン <THE BRAVE ONE>
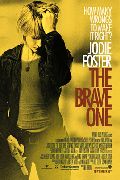
◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★☆
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★★★☆☆
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★★☆☆
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ★★☆
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★☆
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★★★
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★★☆
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★★☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 26点
 <個人的感想>
<個人的感想>
いやぁ、実に素晴らしい映画でした。私はこういう、私刑を肯定する映画って大好きなんですよね。悪党なんて撃ち殺してしまっていいんですよ。社会のダニは抹殺すべきなんです。この主人公の行動は「犯罪」ではなく「掃除」だと思いますねぇ、ええ。
とは言え、倫理的に問題がある行動だというのは私もよく分かってます。これを認めたら、行き着く所は「自分の気に食わないヤツは殺していい」という方に行ってしまって、秩序も平和もあったものではなくなりますからね。
この映画の主人公は、たまたま悪党を見抜く目がありましたけど、もしかしたら「悪党と思われてるけど、実は善人だった」なんて人まで殺してしまう可能性もあるわけですし。
やっぱり、現実には「警察に代わって、法を独自の解釈で執行」というのは間違った事なんだと思います。社会のダニこと悪党連中にも家族がいる場合があるでしょうし、「なぜ、悪に走るようになったのか」という理由に同情の余地があるのかもしれません。
でも、正直、“法”というものにイマイチ信頼がおけないんで、「こんな事、実際には絶対にやってはいけない」とは言いづらいものがあるんですよね。そして、こういう悪党連中に現実に被害を被る可能性のある我々一般市民にとっては、この手の連中を問答無用で撃ち殺すというのは、何だかんだで溜飲が下がる思いがあるんですよねぇ。
それにしても、こんな、ある意味偏った思想の映画にジョディ・フォスターが出ているというのも意外です。
主人公の行動に対して、映画は中立の立場をとってないんですよね。むしろ「映画の中ぐらい、復讐を容認してもいいじゃないか」みたいな、一種の開き直りのようなものも感がられるぐらいです。
最近の世間の流れに逆らっているかのような内容なんで、この映画の存在自体が驚きみたいな所がありますね。私は先にも書いたように、こういう映画は大好きだからいいですけど、この暴力礼賛な内容に不快感を持つ人も多いでしょうね。
でも、個人的には「こんな映画、よく作ってくれた!」という思いが大きいです。復讐の容認だとかそういう事は置いておいて、現実に我々に危害を加える存在である町の害虫をぶち殺すというのは、上にも書きましたけど、やっぱり快感なんですよね。
しかも、この主人公がまた、ためらいも無くバンバン撃ってくれるんですよ。なんて頼もしい(笑)。ほんと、ムシケラを殺してるかのようでした。銃撃の音がかなり大きめのサウンドなんですが、この音が心地よく感じられるんですよね。この音がする時、即ち、悪党が弾を食らった時、というわけですからね。
もう、ちょっとしたヒーロー物映画ですね。だいたい、やってる事はデアデビルとあまり変わってないんですし(舞台も同じNYだし・笑)。で、デアデビルのレーダーセンスに相当するのが、エリカにとっての9ミリ銃なわけですか。
出来れば、続編を作って欲しいぐらいの映画でした。必殺の9ミリ銃はラストで失われてしまうんで、今度はもっと口径のデカい武器を選ぶのもいいかもしれないですな。ジョディはもうやらないでしょうけど、その時は代わりにジュリアン・ムーアを引っ張ってくればいい事ですし(ジョディの後釜と言えば、この人・笑)。
インベージョン <THE INVASION>

◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★☆
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★★★★☆
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★★★☆
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ★★☆
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★☆
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★★★
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★★☆
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★★★
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 29点
 <個人的感想>
<個人的感想>
映画が誕生して100年余ですが、その歴史の中、このストーリーが映画になるのはこれで4度目ですよ。まさに大人気エピソードと言えるわけですが、何故か全米で大コケ(もちろん日本でも)。
という曰くのある映画で、予告があまり面白くなさそうだった事もあって私もほとんど期待していなかったんですけど、これが見てみたら大層面白い映画でビックリしましたね。
何だか小難しい映画が多い昨今、久々に単純にスリルとサスペンスを楽しめる映画で、上映時間も無駄に長くないですし、個人的には大評価したい一作でした。
4度目の映画化ですが、私は過去作は、2作目にあたる『SFボディ・スナッチャー』しか見てないうえに(ドナルド・サザーランドと人面犬が出てくる事でお馴染み)、特に「傑作だ!」とも思いませんでした。なので、リメイク映画特有の「オリジナルと比べてどうのこうの」という感想がほとんど出せない立場なので、その辺りも、この映画を純粋に楽しむ事が出来た一因なのかなとも思います。
ジャンルは侵略物のSFですが、今回のリメイクでは面白い事に、「宇宙人の侵略」ではなく、「宇宙細菌による感染拡大」が描かれているんです。要するに、“敵”に相当する存在がいないんですよね。
感染した人々は、過去作と同様、すっかり別人になってしまうわけですが、ある目的を持って行動するようになります。それは「人類絶滅」とかではなく、逆に「全人類が一つとなって、平和な世界を作る」というものなんです。
何だか、究極の選択みたいでしたね。個性や感情を失う代わりに世界平和をとるか、それとも今のままの荒れた世界をとるか。この、「襲ってくる連中が、もしかしたら敵じゃないのかもしれない」「あるいは主人公の行動の方が間違ってるのかもしれない」と思える所は実に面白かったです。
こうなると、感染者から逃げて抵抗する主人公に感情移入出来なくなる可能性も出たと思うんですが、感染者達がゾンビみたいにワラワラと襲ってきてくれるおかげで、逃げる主人公の姿に「恐ろしい敵から逃げるヒロイン」というパターンが見えて、普通に逃走劇にドキドキしながら見る事が出来ました。
あと、逃げる主人公が、普段生活してる時は入り込まないような場所に逃げ込んだりするのも、何だか見てて楽しかったですね。
「無表情でいれば、他の感染者達を騙しとおせる」「感染しても、眠らなければ変身しない」といったルールもとてもユニークで面白いです。もしこの映画が大ヒットしてたら、町を無表情でねり歩く「インベージョンごっこ」が小学生の間で流行ったりしたのかもしれないですね(それは無いか・笑)。
グッド・シェパード <THE GOOD SHEPHERD>

◎満足度 ★★☆☆☆
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★☆☆
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★☆☆☆☆
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★★★☆
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ★★☆
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★☆
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★☆☆
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★★☆
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 18点
 <個人的感想>
<個人的感想>
実に手強い映画でした。どのぐらい手強かったのかと言うと、「何が言いたい映画なのか」が何一つとして分からなかったぐらいです。
どんなテーマなのか、これを見て何を感じて(または考えて)ほしくて作られたのか、どういうストーリーだったのか、主人公は何を考えていたのか、ジョー・ペシはいったいどこに出ていたのか(エンドクレジットで名前を見つけてビックリ)といった事、全てが分かりませんでした。もうお手上げです。デ・ニーロにお手上げ。
CIA創設に関する歴史物かと思ったんですが、それにしては、肝心の「CIAがどんな仕事を、どんなふうにやったのか」というシーンがありませんでしたし、いつ出来て、どう発展していったのかもよく掴めませんでした。
では、CIAという組織に翻弄された男の話なのかと思うと、これも違う気がするんですよね。まず、先にも書いたように、主人公が何を考えてるのかが見てて分からないんです。一応、仕事と家族の間で揺れ動く素振りは見せるんですがね。
結局仕事を選んでいくんですが、何でここまでこの仕事に、人生を懸ける程の情熱で取り組んでいるのかが分からないんです。ボーンズの会員だから、なんでしょうかね。ともかく、主人公がどういう考えを持っているのか分からないので、共感も感情移入もあったものではありません。
あと、時々時代が飛んだり戻ったりという、『父親たちの星条旗』みたいに時系列がいじくられた編集になっているし、登場人物も多いしとで、ストーリーを追う事自体が困難という状況ですよ。わざと難しく作られてるのか、この映画は。
『シリアナ』もそんな映画でしたが(こっちもマット・デイモンが出てるな)、こういう映画を見る度に思うのは、何でわざわざ話を難しくして、批評家や頭のいい人しか楽しめないような映画を作るのか、という事です。
映画関係者(俳優とか監督とか)には、観客に支持されたい派と、批評家に支持されたい派がいるように思えるんですが、この後者に属する人々は、結局のところ、物語を語りたいとか、世間に訴えたい事があるから映画を撮ってるのではなく、名声とか権威が欲しくて映画を撮ってるんじゃないのかと思ってしまいますね。
映画の内容にあまりについていけなさすぎて、ついこんな穿った事を考えてしまいました。自分の理解力が足りないのを「映画が難しいのが悪い」という方向に持っていってはいけませんね。クレーマーじゃないんですから。そもそも、私自身、事前の情報から「私が見て楽しい映画ではない可能性が大いにある」という予想をしていたにも関わらず、敢えて見に行ったんですし。
で、これだけ文句を言っていながら、実はつまらなかったわけではないんです。多少辛かったですけど(爆)、「金返せ!」的な事は全く思いませんでした。
例えば、“超難解な問題に挑んでいる時”のような、「あ、オレ久々に頭使ってる」と思える、知的なひと時を与えてもらえましたからね。
と言う訳で、またこういう、明らかに難解な映画が現れても、また見に行く事になるかもしれません。何度も挑んでいたら、そのうち、こういう映画の楽しみ方も分かってきて、感想から文句や愚痴が減っていくかもしれませんしね。
パンズ・ラビリンス <EL LABERINTO DEL FAUNO>

◎満足度 ★★★☆☆
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★★
(そのジャンルの映画としてどれだけいい出来だと思うかを主観、客観両面から評価)
◎感情度 ★★★★☆
(笑い、泣き、興奮、恐怖など、見ていて何かしら感情を揺さぶられたかどうか)
◎CAST度 ★★★☆☆
(個人的に、キャスティングに満足いったかどうか)
◎監督度 ★★☆
(監督の演出が個人的に良かったかどうか)
◎音楽度 ★★★
(音楽がどれだけ印象的だったか)
◎期待度 ★☆☆
(見る前の期待にどれだけ応えてもらえたか)
◎体感時間度 ★☆☆
(実際の上映時間より長く感じたか、短く感じたか。短く感じられた方が高得点)
◎リピート度 ★★☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
合計 24点
 <個人的感想>
<個人的感想>
「大人向けのダークファンタジー」という事なので、ある程度暗い映画である事は予想していたものの、いやぁ、まさかここまで鬱な映画だったとは。もしファンタジーの要素が話に絡まなければ、戦時中の可哀相な少女を描いただけという話なんですよね。まあ、そこにファンタジーの要素が絡んでくる所に面白味があるわけなんですが。
でも、ストーリー展開における“幻想世界”と“現実の世界”の出てくる割合が、“現実世界”の方が多くを占めてるんです。戦時中が辛い世界だったのは、ここまで執拗に見せなくても分かってるんで、ファンタジー世界の方を多く見せて欲しかったですね。せっかく映画なんですから、もっと夢のある話が見たかった、というのが正直なところです。
しかも、たまに出てくるファンタジー世界の映像(美術面)が凄くいいんですよね。余計に「もっと見たい!」と思ってしまいます。
このジャンルにしては珍しいぐらい、映像におけるCGの割合が少なくて、どこか、80年代のSFX映画を見てるような懐かしさのある映像なんです。今、ファンタジー映画でこういう雰囲気の映像を見ると、逆に新鮮な感じがしますね。
あと、クリーチャーの造形も素晴らしかったです。結構ホラーチックで、不気味さとおぞましさが感じられるような輩なんですが、特に、中盤頃に出てきた、「手の平に目がついてるヤツ」の造形と動きには感動しました。もう、見てて小躍りしたくなるぐらいに素晴らしいビジュアルのモンスターでした。出来れば、コイツのスピンオフのホラーを作ってもらいたいぐらいです(笑)。
そんな見るも恐ろしいクリーチャーが出てきたりするファンタジー世界の描写より、現実世界の描写の方が全然血生臭いというのも不思議な話でしたね。
ストーリー全般の暗さもさることながら、ラストも、ハッピーエンドなのかバッドエンドなのかハッキリしないものだというのも、この映画を暗くしている要因でしたね。見終わった後に軽く沈んだ気持ちにさせてもらいましたよ。
確かに、よく出来た内容の映画だったとは思いますが、私はこういうのより、『ネバー・エンディング・ストーリー』みたいな明るいファンタジーの方が好きですねぇ。
(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください
 ←前に戻る
←前に戻る
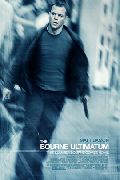 ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>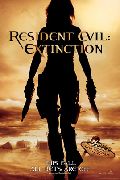 ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>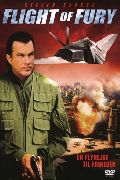 ◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>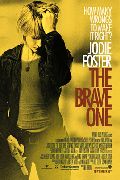 ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ◎満足度 ★★☆☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★☆☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ←前に戻る
←前に戻る