※星マークの評価ポイントは、映画の完成度や客観的評価を表すものではなく、個人的にどれぐらい楽しめたかを表すものです。
シューテム・アップ
<SHOOT 'EM UP>
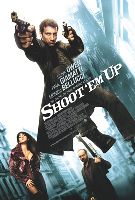
◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★☆
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★★☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★★★☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★☆☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★★★☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★★☆☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★★☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★☆☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ★☆☆☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 32点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
一見、マンガ的でバカバカしい感じの映画なんですが、「ふざけて作った」という雰囲気は全く無く、むしろ、アクション映画として非常に見応えのある一品という印象でした。
他の映画では『トランスポーター』シリーズに近い感じがあるかもしれませんね。あの映画では、冗談みたいな内容のアクションを、主演のジェイソン・ステイサンがいたって真面目に演じているという辺りに面白味が出ていましたが、この映画の主演のクライヴ・オーウェンも同じアプローチを仕掛けてきていました。シリアスな内容だった『トゥモローワールド』の時とほとんど変わらない雰囲気でしたからね(また妊婦やら赤ん坊やらと絡む事になるし・笑)。
オーウェン演じる主人公は、「謎の銃の使い手」といった感じの男で、本名も不明です(一応、スミスと名乗ってますが)。この主人公のキャラクターが非常にユニークで、さらに、超強いんです。どう強いのかと言うと、銃の扱いが凄いというタイプですね。『トランスポーター』のフランクみたいにマーシャルアーツは使わないんですが、代わりに、銃を持たせたら、武装した敵10数人に囲まれても、かすり傷一つ負わずに倒してしまえるぐらいの凄まじさです。
ですが、これは、主人公の銃の扱いが凄いという以前に、「主人公に敵の弾が当たらないようになってる」という裏設定のおかげで強いという面もあったりするんですけどね。結構、敵に至近距離から銃撃されるという局面に何度か遭うんですけど、もう、掠りもしないんですよ。別に避けてるわけでもないんですけどね。むしろ、弾の方が主人公を避けてるのかと思うぐらいです。
銃撃戦はこの映画のメインとも言えるもので、劇中でも数回に渡って登場します。でも、このように、緊張感があまり無い演出になってるんですよね。ここは確かに少々残念ではあったんですけど、その代わり、「主人公が敵をどう倒すか」というのはかなり凝っているんです。むしろ、主人公が敵の弾を避けなくてはいけないという制約が無い分、より自由な攻撃描写が可能になっているといった趣ですかね。
銃撃が始まると、必ず、主人公は大勢の敵に囲まれているという状況になるんですけど、その大勢の敵をいかに殲滅していくか、という攻撃アクションは映像的にもかなり映える、面白いものになっていました。
シチュエーションが凝ってる場合もあり、「出産の手伝いをしてる最中に銃撃戦」とか「SEXしながら銃撃戦」とか、もう悪い冗談としか思えないようなアクションシーンが出てきたりします。この状況設定だけ聞くと本当に悪い冗談ですけど、映画全般において、そういうシーンが出てきても悪くないような世界観になっているんで、特に違和感を感じるような事もないんですよね。
そして、「かなりマンガチックで、見てて笑える」というアクションシーンが多いんで、もしかしたら『少林サッカー』の精神に近いものがあるのかも、なんて事を思ってしまいました。まあ、こちらは過剰なCG合成やワイヤーは使っていないですけど、「現実離れした派手なアクションで笑える」という辺りは共通するものがあるように思えます。ただ、この映画の場合、先にも書いたように、クライヴ・オーウェンの演技がいたって真面目なので、“アクション・コメディ”という雰囲気が無いというのが面白い所ですね。
さて。先にも書いたように、主人公は大変ユニークなキャラクターで、ただ強いだけではないんです。
まず、その銃の腕が確かな理由付けの一つとして、「非常に視力がいいから」というのがあるんですが、その為に、視力にいいと言われているらしいニンジンを、暇さえあればかじっているんです。ニンジンが目にいいなんて聞いた事ないんですけど、本当なんですかね(ブルーベリーが目にいいというのはよく聞くんですが)。しかもこの男、実は普段は銃は持ち歩いてないんですけど、ニンジンは常に携帯してるんです。よっぽどニンジンが大好きなんでしょうねぇ(笑)。
そして、社会のマナーに大変厳しい性格をしていて、「障害者用駐車スペースの不正利用」や「ウィンカーを出さずに無理に車線変更をする車」なんてのを見つけたら、「車の盗難や破壊」といった罰を与えてやったりするという、ちょっとした世直しマンの面もあるんです(やり過ぎですけど・笑)。
そもそも、事件に関わるきっかけとなったのが、「バス停でニンジンをかじってたら、目の前を、銃を持った男に追われる若い妊婦が通っていった」というものでしたからね。「何だ、このいい加減な導入部は」とか思ったものでしたが、でも、このストレートさがこの映画の味なんですよね。この導入部も、あまりにも堂々と描いてくるんで、何か、ここで自然と映画の世界(と言うか、この映画のノリ)に引き込まれてしまいました。
一方、ポール・ジアマッティ演じる敵のボスもまた、主人公に負けず劣らずのユニークなキャラクターでしたね。セリフとかも面白いんですけど、「元FBIの心理分析官」だか何だかで、追う相手が何者なのかとか行く先とかを推理出来たりするんです。
と言うわけで、「どう逃げても追いついてくるジアマッティ」「襲い来る敵を殲滅するオーウェン」が延々繰り返されながら、合間にストーリーが進んでいくみたいな感じになっていて、もう、何も考えずに、二人のユニークなキャラクター同士のせめぎ合いを楽しく見ていられるという、そんな愉快な映画でした。
JUNO/ジュノ
<JUNO>
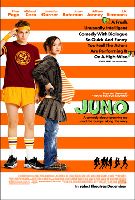
◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★☆
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★☆☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★★★☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★★☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★★☆☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★☆☆☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★☆☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★☆☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 28点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
「10代の妊娠」というテーマを扱う場合、普通はやたら重くて深刻な話になりそうなイメージがあるんですが、それを、ライトなコメディタッチで仕上げたというのが、何か珍しいなと思ってしまいます。
何で重くならないのかと言うと、妊娠した当のジュノが、前向きでユニークな性格をしていて、精神年齢も二十歳超えてそうな雰囲気がある、という事で、この問題に対処出来そうな気配があるんですよね。
ただ、一人ではさすがに対処出来なかっただろうと思いますが、周囲がいい人ばかりなんですよ。両親も、娘の妊娠を知っても怒ったり呆れたりといった態度を全く見せずに助けてくれますし、相談に乗ってくれる親友もいます。そして、ジュノを孕ませた男の側も、ロリコンの遊び人みたいな輩とかではなく、同級生の、今だに童貞っぽさの抜けてない純な好青年みたいな奴でしたからね。悪い奴、嫌な奴が周囲に一人もいないという状況ですよ。これでは、むしろ重くなりようがないみたいな状況です。
さて。妊娠発覚後、子供を産む決心はしたものの、「自分では育てられない」という事で、赤ん坊は里子に出す事にするんです。で、里親を探す事にするんですが、これがあっさりと見つかったうえに、また、やたらといい人達なんですよね。この映画の「いい人登場率」の高さは相当なものだと思いますよ。
そんな状況なので、最後は当然のようにハッピーエンドで終わる事となります。里親の夫の方とジュノが趣味が似ている、という事で仲良くなり、「ジュノの気持ちが、この夫に傾きかけ・・・」みたいな、「おいおい、これからどうなるんだ」と思うような流れも見せてきますが(ちなみに、この二人の「ホラー映画談義」は渋くて面白かったです)、ドロドロした方向には当然行かず、最終的には、主要登場人物みんなが幸せを手にして終わるという(多少の失うものは出てくるものの)、見終わった後に爽やかな気分になるラストです。いやぁ、いいですね、平和的で。
ただ。一人だけ、「この人は本当にこれでハッピーなんだろうか」と思ってしまう人物がいました。この人以外の主要登場人物は軒並みハッピーエンドだったのに、です。
その人物とは、まあ、ジュノの産んだ赤ちゃんなんですけど、将来、「産みの親に捨てられた」的な悩みを持ったりとかしないんだろうか、というのが気になってしまいました。
実は、この映画の登場人物の誰一人として、この件に触れてこないんですよね。むしろ「赤ん坊の譲渡」がさも当然の事のように話が進んでいくんです。
劇中、ジュノには「中絶か里親か」という選択肢が出てきていたんですが、何で2択なのかと。「皆の協力の元、ジュノが自分で育てる」という選択肢が何で全く出てこなかったのかが分からないんですよね。そっちの選択も十分可能と思える環境と、私には思えたんですけど(何しろ、周囲はいい人ばかりなんですから)。
確かに、これが一番大変な選択ではあると思いますし、もしかしたら、私が気付かなかっただけで、「ジュノがこの事について葛藤をしていると思われる場面なりセリフがあった」という可能性もあるんですけど、映画を見終わってしばらくしてから、「もはや、“赤ん坊が誰に育てられるのか”というのは、さほど重要ではない時代になってきてるんだなぁ」と思って、何だか寂しい感じがしてしまいました。見終わってすぐの頃は爽やかな気分だったのに(笑)。
ですが、後半に、家族の絆というものについて考えさせられる箇所が出てきていたんですよね。ジュノの回りの大人は結婚を失敗した人ばかりで(と言っても、2組ですけど)、「一生一緒にいられるような人を見つける事なんて出来ないんじゃないのか」みたいな悩みを持ち始めるみたいな流れがあって、そこで、「自分の全てを、あるがままの姿で受け入れてくれる人を見つければ、“壊れない家庭”を持ち続ける事が出来る」みたいな内容の話が出てくるんです。
これは、一見、10代の妊娠とは別の問題の話のようにも思えますが、「家族の絆には血の繋がりよりも大事なものがあるのではないか」というメッセージのように思えるんですよね。それは、夫婦間ばかりの話ではなく、親子間でも言える話なんじゃないのかと。血の繋がりが無くても、愛情があれば幸せな家庭を築いていける、と言うのなら、「“赤ん坊が誰に育てられるのか”というのは、さほど重要ではない」という事に対しても、少しは前向きに思える事が出来そうな気がします。
REC/レック
<[REC]>
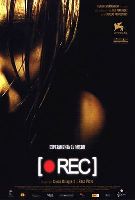
◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★★
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★★☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★★★☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★☆☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★★☆☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★★★☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★★☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★★☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ★☆☆☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 34点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
手持ちカメラの目線から全てが描かれるという、『クローバーフィールド』と同タイプの手法が使われた映画です(実は、製作はこっちの方が先らしい)。
『クローバーフィールド』公開時、「ゾンビ映画をこの手法で撮ったら、面白いのが出来やしないだろうか」と妄想していたんですが、この映画、まさにそういう内容なんですよね。何だか、個人の夢が本当に形になったみたいで、妙な嬉しさがあったものでした。
でも、実際に見てみて、別に、この主観撮影方式で全編撮らなくても成立する映画なんじゃないか、とか思ってしまいました。あんまり「この手法ならでは」感が無かったんですよね。カメラマンが移動するシーンでは画面がまたやたら揺れるという弊害も出ますし(それでも、感染者襲撃シーンなんかは『28日後』や『28週後』より全然見やすかったですけど・笑)。
あと、「もしカメラマンがやられたり、カメラがぶっ壊れたりしたらもう後の展開を見られなくなる」という、本来感じなくてもいい不安感を感じるハメになりますからね。
別に、主観撮影を使わなくても、「主人公の目線で全てを描写する」という事は出来るわけですし、また、「主人公には分からないけど、背後から危機が迫っている」みたいなサスペンス場面を入れる事も出来るわけじゃないですか。
もちろん、所々に、この手法ならではの面白いシーンとかは出てくるんですけど、「もしかしたら、この手法のおかげで表現出来なかった怖さがあったんじゃないか」という思いが出てきてしまいましたね。
とは思ったものの。ゾンビ系ホラー映画としての出来は恐ろしく高い映画です。何しろ、怖いんですよ。手法がどうとか関係なく、「肥えた老婆が奇声を発しながら襲ってくる」なんて、嫌過ぎでしょう。老婆に限らず、感染者達の声もかなり恐ろしいものなんですよね。
あと、「狭いアパート内で、住人が次々凶暴化していく」という、舞台が限定されてる辺りも恐怖感を強く煽ってくれる点でした。この、狭くて逃げ場の無い場所で、見るからに凶暴な元人間が、聞くも恐ろしい奇声を発しながら襲ってくるというのは、かなり厳しいです。
そして、「怖い場面をどう見せるか」というのがちゃんと考えられているのが凄い所です。実は、この映画の怖さは、映像よりも演出面が優れてるからこそ感じられるものがほとんどだったように思えるんですよね。
思えば、監督のジャウマ・バラゲロの前作『悪魔の管理人』も、怖いのと同時に、その見事な恐怖演出に感心してしまうような映画でしたからねぇ(そう言えば、またアパートが舞台の映画なんだな・笑)。
この主観撮影も、もしかしたら、下手な人が撮ったら、ただ見辛いだけの、ストレスが溜まるような映画になってたかもしれないんですよね。多分、ジャウマ・バラゲロが監督だったからこそ、この映画はこんなにも怖い映画になったのではないのだろうか(この人の他にもう一人監督がクレジットされてるんですが、こっちは何者なんだ)。
今後、この手法の映画が流行りそうな予感ですが、その中から面白い映画が果たして何本出てくる事か・・・。アメリカでは早速この映画のリメイクが作られたようですが、ここまで怖い映画になってるかどうか(笑)。
最後に、どうでもいい事ですが、消防士って、火事だけでなく、ゾンビパニックが起こった時も頼りになる人達なんですね(笑)。
インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国
<INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL>
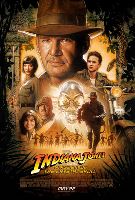
◎満足度 ★★★★☆
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★★
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★★★☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★★★☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★☆☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★★★★
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★★★★
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★★★☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★☆☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ★★★☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 39点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
全世界待望の『インディ・ジョーンズ』シリーズ最新作ですが、以前からこのサイト上でもちょくちょく言ってましたが、実は私はそんなに待望してませんでした。
もう、自分の中で神格化されてるシリーズなんで、「老いたハリソン」「最近、娯楽映画らしい娯楽映画が撮れなくなったと思われるスピル」のコンビで今『インディ』を作っても、本当に満足出来るような映画が作れるとは思えなかったからでした。
でも、予告編を見てみたら、まさに「あの頃の『インディ』」といった雰囲気が感じられて、一気に「これはイケるのでは!」という期待感が出てきたんですが、まあ、結局見てみたら、当初心配していた通りの映画だったという・・・。
もちろん、アクション・アドベンチャー映画としては非常に面白い、よく出来た映画ではあったんですよ。もし私が「思い入れ」という曇ったメガネで見ていなければ大満足できたはずのものなんですけど、でも、私がこのシリーズに求めていたのは、「非常に面白い映画」程度のものじゃなかったんですよねぇ。過去3作の初見時の印象と、今回シリーズ初の映画館での鑑賞だというのを考えると、「あまりに面白すぎて、見てて死ぬ」ぐらいのものであって欲しかったんです。
いやまあ、もちろん死んだら困りますんで、そこまで凄くなくてもいいんですが、何か、もうちょっとどうにか出来なかったものなのかなぁ、と思ってしまうんですよねぇ。
「これは自分の見方が悪かっただけで、もっと落ち着いた気持ちで見れば満足出来るに違いない」と、感想書きも2回目の鑑賞を待ってから書く事にしたんですが、結局、2回目を見て、さらに「過去3作に劣り過ぎる」という印象が強くなってしまいました。もう、これまでのシリーズと完全に切り離して、別物として見た方がいいのかもしれないですね(主要スタッフ&キャストが同じシリーズなのに・・・)。
では、具体的にどの辺りがイマイチと思ったのかと言いますと、やっぱり、まず第一に「インディの老化」ですね。
実のところ、ハリソンのアクション自体には特に衰え的なものは無くって、もし、10年前に作られていたとしても、アクションの量も質もほとんど変わらなかったんじゃないかと思います。
でも、動きは良くても、外見や立ち姿が、もう何か完全に“お爺ちゃん”なんですよね。人間誰しも歳とるものですし、あの年齢になっても相変わらずの冒険野郎だった老インディの姿は頼もしくもあったんですけど、同時に、あまり見たくなかった姿でもあるという何とも複雑な心境です。もしかしたら、私にとってハリソン・フォードは「歳をとっても渋い系」の俳優ではないのかも。
あと、ストーリー面も、あまり「冒険をしてる」「宝を探している」といった雰囲気が感じられなかったんですよね。まあ、この辺りは前作『最後の聖戦』でも感じた事なんですけど、前作には「コネリーパパとの珍道中」という、それを差し引けるような面白い要素がありましたからね。
それに、クリスタル・スカルのパワーで頭がイカれた、インディの友人の学者が、「ほとんどの謎を先に解いていた」というのもちょっとガッカリでした。
さらに、インディ御一行の人数も多すぎるんですよね。敵も団体さんですし、何か、ごちゃごちゃした感じがありました。私がこのシリーズに求めてたのは「インディの活躍する姿」なんですが、キャラが多すぎて、肝心のインディの活躍が埋もれがちだったんですよね。
一方、「良かった点」というのもちゃんと挙げておきましょう。このままでは「期待を裏切った大駄作」の感想みたいですが、実際は39点という高得点を叩き出してる映画なんですから(上半期は35点が一つの壁だったのに、軽く越えてきましたからね)。
まずは、先に「良くなかった点」としても書いた所なんですけど、何だかんだ言っても、インディが「老いてもなお健在」な元気があったというのは良かったです。歳をリアルに表現しようとして、多少覇気が落ちてるみたいなキャラになってたらさらにガッカリしてたところですからね。
ムチを使ったアクションもちゃんとやってましたし、銃を持った敵の只中に突っ込んでいったり、洞窟内で無類の頼もしさを見せたりといった姿は「やはりこうでなくては」と思いましたね(これで、ハリソンがもうちょっと若かったら、、、)。
あと、個人的に邪魔なキャラが多かったと思った“インディ御一行”の中、シャイア・ラブーフは結構光ってたと思いますね。キャラクター的にも、性格面にこそあまりこれといった特徴が感じられなかったんですが、衣装や髪型には個性が感じられましたし、ナイフやクシといったパーソナルアイテムが存在する辺りも面白いです。インディのムチと帽子みたいな感じで。
そして、以外にこの人、アクションのセンスが結構あるんですよね。中盤のジャングル内のチェイスシーンでは思いっきり見せ場をさらっていってましたからねぇ。
ちなみに、このシリーズには代々、一ヶ所もの凄いテンションの「最大の見せ場!」的なアクションシーンが登場しますが(クライマックスの直前ぐらいで)、今回のこのジャングルチェイスも、過去作に勝るとも劣らない、それは凄いアクションシーンでした。もう、見てて大興奮でしたよ(ただ、そこでメインに活躍するのがインディじゃなくなったという、残念な面もあるんですが、、、)。
ラスベガスをぶっつぶせ
<21>
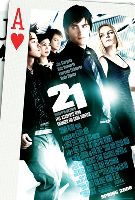
◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★☆
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★☆☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★★☆☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★☆☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★★☆☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★☆☆☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★☆☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★☆☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 26点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
“数学の天才”という若者が、“カードゲームで金を稼ぐ”という、10年前ならマット・デイモンが主演しそうな内容の映画です。
“カード・カウンティング”と呼ばれる、ブラックジャックの必勝テクニックが公開されるわけですが、これがもう、「天才専用」みたいなもので、私クラスになると、もはや説明を聞いても何がどうなってるのかサッパリみたいな状況でしたよ。多分、すでに見えてる札から、次の来る札を確立の計算で導き出す、みたいな感じだったと思うんですが、これで合ってるのかどうか。
まあとにかく、主人公がとんでもなく天才だという事はよく分かりました。しかも、顔もハンサムときたもんだ。普通なら「このエリートめ」とか思うところなんですが、天才ハンサムにも関わらず、全然イヤミな感じがしないんですよね。どちらかと言うと、オタクっぽい雰囲気で、むしろ親しみやすいキャラといった感じでした。
で、スペイシー教授からカード・カウンティングのクラブにスカウトされ、仲間と共にベガスで金を稼ぎに行く事になるわけですが、主人公の「なぜ金が欲しいのか」の理由が、「学費を稼ぎたいから」というのが素晴らしいですね。まさにミスター・品行方正。
ギャンブルなんかにハマらなそうな雰囲気ですし、本人も「学費に必要な額を稼いだら辞める」と宣言しています。今までの態度から、その発言に説得力もありますし、「コイツなら大丈夫だろう」と思っていたんですが・・・。
いやぁ、金の力というのはほんと恐ろしんですねぇ。こんな、純な好青年ですら、快楽の魅力に取り付かれ、今までのナイスガイの部分が段々と薄くなっていくんです。
「金は人を狂わせる」とはよく言うものの、私なんかには当てはまらない事だろうと思っていました。大金を容易く、合法的に手に入れられるという環境におかれたとしても、金に振り回されるような事にはなるまいと。冷静な対処も出来るだろうと思っていたんですが、“冷静かつ天才なナイスガイ”が、こうして目の前で金の魅力に負けていく様を見ると、「オレは金を侮っていた!」と戦慄せざるを得ません。
ですが、この映画は天才が落ちぶれていく様を描くという内容ではなく(そんな内容なら、『ラスベガスにぶっつぶされた!』というタイトルになっていた事でしょう)、むしろ、「人生のピンチも、冷静に対処すれば切り抜けられる」という、ポジティブなテーマを含んだ映画なんです。
なので、主人公がどん底に叩き落された後から、この映画は面白く、そして気持ちよくなっていくんですよね。
誰しも、嫌な事は経験したくないですが、それをプラスに変えて、これからの人生をより良いものにしていく事も出来るんだな、というのが感じられる、非常に爽やかな映画でした。
爽やかと言えば、主人公の友人のロボットオタク(と言っても、アニメ等にハマっているわけではなく、作る方に凝ってるタイプです)の、“イイ奴っぷり”の清々しさといったらなかったですね。
主人公は、見てて「羨ましい」と思えるタイプですが、この友人は「こういう人間になりたい」と思わせてくれるタイプでした。
ちなみに、カード・カウンティングは合法の技らしいんですが、それを使っていると、逮捕はされないものの、怖い人達に別室(倉庫みたいな所)に連れて行かれて、イタイ目に遭うというのは笑いましたね。なるほど、こういう所では「合法でもやらない方が賢明な事」というのがあるんですね。
ナルニア国物語/第2章:カスピアン王子の角笛
<THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN>

◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★★
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★★☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★☆☆☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★☆☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★★☆☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★★★☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★★☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★★☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ★☆☆☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 32点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
全世界待望の、ファンタジー大作第2弾です。ですが、私の中の期待度はそれほどでもありませんでした。それは、この手の映画に飽きているから、というわけではなく、「前作が期待ほど楽しめなかった」というのがあったせいでした。面白かった事は面白かったけど、私にはちょっと刺激が足りなかったかなみたいな。
で、個人的に「2作目ではここを改善していて欲しい」と思っていたのが、「戦闘シーンをもっと派手で荒々しくして欲しい」「主要キャラをもっと魅力的に描いて欲しい」「もっとイノシシの出番を増やせ」といった点でした。
その内、2番目の「主要キャラの魅力」は前作とほとんど変わらずで(まあ“魅力が無い”というわけではないんで、いいんですが)、3番目の「イノシシの出番」に関しては、イノシシ自体が出てきませんでした。無念。一瞬、それらしき後姿を見たような気もしたんですが、もし参戦してるんならもっと多く画面に映ってるはずなんで、きっと気のせいだったのでしょう。
とは言え、「合戦シーンに動物達が参戦している」という点は、やっぱりユニークで面白いものでした。今回はナルニアが滅びかけてるみたいな状況なので、種類こそ前作より減りましたが(おかげでイノシシもカット)、ヒョウとか(トラだったかも)クマといった戦闘的なのもちゃんといますし、人を運べるぐらいデカい鳥がいたり、シカみたいなのがいたり(こいつらは戦闘中、何かの役に立ってたんだろうか・笑)と、視覚的に大変賑やかでした。
中でも、クマは面白い動きを見せていましたね。時々、画面の隅で愉快なリアクションを見せてる時があるんです。一騎打ちのシーンでハラハラしてるようなしぐさをしていたり、ラストでは主人公達に軽く手を振っていたり。もしかしたら、『ライラの冒険』でのシロクマの活躍を見たCGスタッフ達が、「クマの動きって意外と面白いな。よし、我々もクマを出そう」みたいなノリで加えられたキャラだったりして。
さて。希望していた3つの改善点の内、2つがスルーされてしまいましたが、そんな中、一番目に挙げた「戦闘シーンの迫力」面に関しては、今回、大幅に向上されていたんです。何しろ、ここが一番重要な点なので、これは嬉しかったですね。おかげで、期待以上に楽しむ事が出来ました。
前作に比べて「ファンタジー度」よりも「アクション度」が重視されてるような感じになっていて、脇の登場キャラも、前作のタムナスさんに相当するのが「剣を振り回す、やさぐれた小人」なんてのになりましたからね(敵も、“魔女”から“野心満々のおっさん”になりましたし・笑)。
主役の少年少女も、前作のラストで長らくナルニアに王として留まっていた間に得ていた経験値が残っていたようで、子供ながらにして大人の戦闘力を持つという状態で登場しているんです。なので、率先して敵国に攻め入ろうとしたり、敵の大将に一騎打ちを挑んだりと、もう、「お前は戦闘民族か」と思うぐらいの勇猛さを見せてくるんです。おかげで、単純に戦闘シーンの量自体も前作の3~5倍ぐらいに膨れ上がり、さらに、演出面に関しても、相変わらず血は出ないものの、荒々しさの感じられる、迫力のある戦闘シーンになっていたんです。
いやぁ、こういう、「前作より派手になる続編」というのはいいですね。特に、大将との一騎打ちシーンと、クライマックスの合戦シーンは、かなりの迫力がありました。
ただ、前作の敵はモンスターみたいな連中だったところ、今回は人間の兵士が敵として襲って来る事になるんですが、10代の少年少女が、同じ人間である敵兵士を次々と躊躇いもなく屠っていく姿には、やっぱり違和感がありますね。人の命を奪う事に関する葛藤が全く見られないんです。兵士として生活する為に毎日必死に体を鍛えているんであろう人達が、女子高生ぐらいの歳の少女に弓矢で射殺されまくる姿には、何かやるせないものを感じてしまいます。
まあ、主人公達は外見は子供ですが、過去にナルニアで大人として生活していた時の記憶も残っているわけで、中身は大人のはずなんですよね。でも、普段の態度が、とても「一度大人を経験してる」とは思えないような子供っぽさなんで、見た目通りの“子供”としてしか見られないのが困ったところでした。
でも、ペベンシー兄弟のアクションシーンの動きが、本当に強そうに見えるような、見事な振り付けになっていたのは幸いでした。外見はともかく、動きに関してはちゃんと歴戦の勇士みたいに見えるんで、これのおかげで違和感も大分和らげられていた事と思います。ついでに、「異世界に行ったら戦闘力もパワーアップする」みたいな印象も感じられて(そういう設定は無いんですが)、何か「夢があっていいな」なんて思ってしまいました。
あと、この映画を語るうえで避けて通れないのが、新キャラであるイケメン王子こと、カスピアン王子です。基本的に、若いイケメン俳優とかにはあまり興味が無いんですが(30代以降のハンサム俳優なんかは大好きなんですが・笑)、やはり、ファンタジーや時代物の映画に出てくる王子様は整った顔をしてないと締まらないですからね。
ポスター等でも大きく扱われていましたし、「いったい、どんな活躍をするんだろう?」と思っていたんですが、ストーリー上の主役はペベンシー兄妹達の方になるわけなので、何か、微妙なポジションといった感じの、居心地の悪そうな立ち位置にいるように見えてしまいましたね。
でも、ペベンシーの長男と主役の座を密かに争ってるような雰囲気が漂っていて、この二人が一緒に出ているシーンは、何か妙な緊張感がありましたね。他の映画ではあまり味わえないタイプの緊張感なんで、何だか面白かったです。
で、最終的には「良きライバル」みたいな感じの関係に落ち着いて、クライマックスでは共に絶望的な戦闘(アスランがさぼって中々現れない為・爆)に身を投じるという辺りはかなり燃えましたね。
今回、戦闘シーンが多くて、前作よりもファンタジー度が薄い、という印象だったんですが、ラストは「ファンタジー大作を見た!」という満足感の得られる、非常にキレイな終わり方でした。
前作と同じ、「ナルニアから元の世界に戻ってきた」というものなんですけど、ナルニアに行っていた間、現実世界では時間が止まっていた為に、ナルニアでやり遂げた事に関する満足感と共に、「今までの大冒険がもしかしたら夢の中の話だったのかな?」と一瞬思ってしまうような、少し寂しげな感覚が同時にあるんですよね。何だか、上質のファンタジーを見たような気にさせてもらえる、素晴らしいラストでした。
ランボー 最後の戦場
<JOHN RAMBO>
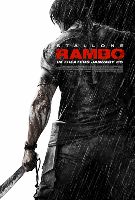
◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★★
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★★★★
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★★★★
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★★★☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★★★☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★★☆☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★★★★
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★★★
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ★★★★☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 45点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
いやはや、かなり強烈な映画でしたね。今までのシリーズはアクション映画でしたけど、今回はもう戦争映画ですね。戦場の規模こそ小さいものですけど、その陰惨さは『プライベート・ライアン』にも決して劣るものではありませんでした。
で、なんで『ランボー』のシリーズでわざわざここまでの残酷絵巻を描かなくてはならないのかという点ですが、それは、「ミャンマーの現実をみんなに知ってもらいたい」という意図があるからなんでしょうね。ただ「面白かった」で終わる映画ではすぐに忘れられてしまいますが、「嫌なものを見た」というのは結構後に引きますからね。それに、現実のミャンマーを知る人によると、実際はもっと酷かったりするらしいですし。
ミャンマーの軍人達は、もう血も涙も無い殺戮集団として描かれ、人間味のかけらも感じられません。「本当に、人はここまで残酷になれるんだろうか」と思うぐらいです。でも、きっとなれるものなんでしょうね。
しかし、一方のランボーもまた、殺しのプロであり、冷酷な殺人マシーンの面を持っているんですよね。
実際、ランボーの攻撃で倒された敵達も、粉々の肉片と化すという残虐な死に様を見せるんです。普通、ランボーが敵を倒せば、観客は拍手喝采みたいな感じになる所なんですが、いや、実際、ランボーが動き始めた瞬間はそんな感じなんですが(ランボーが最初に弓矢で攻撃するシーンを見た時は、興奮してガッツポーズしかかりましたからね)、その“正義のランボー”の殺戮が、敵がやった事と同じぐらい残酷に見えてくるんです。
戦闘中だけでなく、戦闘が終わった後の戦場の描写も抜かりがなく、気持ち悪い死体がいっぱい転がってるという、もう、画面から死臭が漂ってきそうなぐらい強烈な映像を出してきます。「暴力の過ぎ去った後」までもしっかり描いてくるんですよね。
このように、過剰なバイオレンス描写で、逆に暴力の恐ろしさを描いている、という面もあるんですが、「非暴力主義」のキャラクターを通して、「そういうキレイごとが通じない世界もある」という現実もまた見せてくるんですよね。何だか、反乱軍が武力で国を奪い返すとかしない限りどうにもならない場所のようにも思えますし・・・。
ともかく、この映画の残酷描写に対するリアル志向は、「ミャンマーの現実を見せる」という為だけでなく、“暴力”や“殺人”というものについて観客に考えさせる為にも必要なものだったんでしょうね。
でも、こういう演出をされると、アクション映画に不可欠な“爽快感”というのが無くなってしまいます。ですが、この映画の場合、何しろ、主人公が最強の一人軍隊ことランボーなわけで、ランボーの活躍それ自体にはきちんとアクション映画的爽快感があるんです。
歳のせいか、今までのシリーズと比べるとランボーのアクションシーンが相当減りましたけど、その少ないアクションシーンのどれもが、凄い活躍を見せる興奮のシーンになっているんです。ほんと、もう強いこと、強いこと。しかも今回、今までのシリーズにあったような、「敵にとっ捕まる」みたいなシーンもなく、敵に遅れをとるような面を一切見せない、まさに鬼神のごとき戦闘力を見せ付けるんですよね。
あれだけリアルに戦場を描いていながら、主人公のランボーはかなりファンタジーに描かれているというギャップがあるにも関わらず、映画からランボーが全く浮いて見えないんです。多分、「敵を一人で壊滅させてくれるぐらい強いヒーロー」を望んで見ているせいなんでしょうね。ランボーが戦闘を開始するまで結構時間が掛かるんで、それまでに、虐げられたり無残に殺されたりする人々が沢山出てくるわけです。そんな地獄絵図があった後にランボーが暴れだしてくれるんで、もう、こちらとしたら「ランボー、スゲェ!」としか言えなくなるわけですよ。今まで散々と暴虐の限りを見せていたミャンマー軍を蹴散らしていくランボーの姿は、ほんと見てて溜飲が下がる思いです。ただ、その後に「でも、気持ち悪い」と思うことになるんですが。
と、まさにアクションヒーローな無敵さを見せるランボーですが、その内面の葛藤をしっかり描いているんで、人間味というのが強く感じられるようになってるんです。だから、このリアルな戦場を描いた映画にも違和感無く溶け込んで見えるんでしょうね。
ただ、いくらランボーが強いとはいえ、60歳であれだけ動けるというのはちょっと無理があるのではと思ってしまう方もいるかもしれませんが、スタローンの完璧な役作りとアクション演出の上手さのおかげで、映像的にもしっかり説得力が感じられるんです。まず、普段の立ち居振る舞いやら表情からして、「只者ではないオーラ」が出まくってましたからね。もはや老人ではなく、戦士にしか見えません。
あと、仲間となる「5人の傭兵隊」も、いい引き立て役になってましたね。年齢的にも経験的にも申し分無い、「戦い盛り」な連中なのに、そいつらよりもランボー1人の方がはるかに強いという(笑)。これは、この人達が弱いというわけではなく、現実的なキャラ設定をされてるという事なんでしょうね。傭兵隊達の戦闘能力とか、ああいう場での行動とかは、誇張のされてない、リアルな姿だと思うんです。普通の戦争映画とかだったら、この人達が主役的ポジションにいる事になってたのかもしれません。
そして、本来なら有象無象扱いでも十分なこの傭兵隊、一人一人に、きちんとした背景が設定されてるというのも面白い点でした。中でも、スナイパーの“スクールボーイ”はいいキャラでしたね。実際、5人の中では見せ場も多いんですが、特に、この人の“スナイパー”という職種がいいですね。昔はそうでもなかったんですが、最近、狙撃兵を見ると燃えてくるんですよね。遠距離から敵を一発で仕留める姿がカッコいいなぁと。
と言うわけで、ただのアクション映画ではない、非常にパンチの効いた一作という印象の『ランボー』最新作でした。
シリーズの常連だったトラウトマンとジェリー・ゴールドスミスが抜けてしまいましたが、代わりにスタローン自身が監督を務めた事で、シリーズの中で「番外編」という印象の無い、本当の、正統な続編というように思えました。これは『ターミネーター』や『ダイハード』の最新作には抜けてた面でしたからね。
ちなみに、このシリーズにブタが出てくる時は大抵損な役回りをさせられているんですが(『3』では出ませんでしたが)、今回も、シリーズ中で最も出番のシーンが多かったにも関わらず、気の毒な使われ方をされていましたね。ブタも、悪い奴に飼われると、まるで汚らわしい生き物みたいな扱いになってしまうんですねぇ。
結局、『1』でランボーに食われた野豚が、一番マシな使われ方だったのかなと思えてきます。
チャーリー・ウィルソンズ・ウォー
<CHARLIE WILSON'S WAR>

◎満足度 ★★★☆☆
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★☆☆
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★☆☆☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★★★☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★★☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★★☆☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★☆☆☆☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★☆☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★☆☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 23点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
ジャンル的には“社会派コメディ映画”という事になると思うんですが、あんまりコメディっぽい所が無かったような気がしましたね。どちらかと言うと、トム・ハンクス演じるチャーリー・ウィルソンの言動が面白いだけという感じで。やっぱり、気軽に笑い飛ばせないような問題を描いているせいなんでしょうかね。
さて。このチャーリー・ウィルソンという人は実在の人物らしいんですが、「本当にこんな議員がいるのか」と思うような、愉快なおっちゃんなんですよね。朝から酒を飲んだり、怪しいパーティでストリッパーとジャグジーに入ったり。でも、そういうイケナイ事をしているのに、「悪い議員」という雰囲気が無いんです。立ち居振る舞いから、知的で、さらに人好きのする感じが漂っていて、むしろ魅力的な議員と思えるぐらいなんです。
これは、トム・ハンクスが演じてるから嫌味に見えないという面もあるんでしょう。同じ事を脂ぎったオヤジがやってたら、ただ醜悪なだけだと思います。でも、映画を見てると、本物のチャーリー・ウィルソンもこんな雰囲気の人物なんだろうなというのが感じられるんですよね。秘書に美女軍団をはべらせていても許されるような人なんだろうなと。
どうでもいい事ですが、この秘書軍団が、何か仕事が楽しそうで羨ましかったですね。チャーリーよりも、むしろこのチャーリーズ・エンジェルの方に羨望を感じてしまいましたよ。もし私が“そこそこ有能な美女”として生まれてたら、こういう職場で働きたいものです。
で、このチャーリー議員がどういう仕事を成し遂げたのか、というのが描かれるんですが、この、「ソ連がアフガンに侵攻していた時、アメリカがアフガンに武器を流し、兵士を鍛えていた」という話はどこかで聞いてました。でも、それがチャーリーの仕業だったとは知りませんでしたね。
チャーリーが色々な工作をして予算を作ったおかげで、アフガンにそういった援助が出来たわけです。そして、そのおかげで、ソ連はアフガンへの侵攻を諦めて撤退をするに至ったわけで、この時点までは、世界平和に貢献したと言っても過言ではない働きをしたわけです。
でも、その後、アフガンをほっぽらかしにしたおかげで、アメリカを憎むテロが育つような事になってしまった、という結果になってしまったようですね。チャーリー自身はアフターケア的な事をやろうとしていたんですが、戦いが終わると他の議員(金づる達)が途端にアフガンに興味を持たなくなって、予算を集められなくなってしまうんです。
他の国の問題に介入するだけして、問題の解決まで付き合わずに途中でとっとと去ってしまうという、このアメリカのやり口は、どうにかならんものかと思いますね。かと言って、最初から全く何もしないというのもどうかと思いますし・・・。
この映画で描かれる話は80年代の事なんですが、こんな昔話を今更引っ張り出して映画にした意図というのは、やっぱり、今アメリカがそのツケを払わされているから、という事なんでしょうかね。それとも、また同じ事をやろうとしているからなのか。
どちらにしろ、「それはアメリカの問題だ」という気がして、映画としての面白味にはちょっと欠けてたような印象でした。この事件を教訓として何かしらのメッセージを発してる、というのが感じられれば、自分の身近な問題に置き換えて「私も気をつけよう」みたいな事を思えるんですけど、何と言うか、アメリカの歴史の教科書を読んでるだけみたいな感じがあったんですよね。
チャーリー・ウィルソンという人物に対しても、人間性に関する言及が少なくって、伝記映画としての側面がほとんど無いんです。多分、映画の目的がチャーリー自身を描くことではなく、近代アメリカの歴史を描く方にあったんでしょうね。こういう、現存してる人物を描いた映画では、ラストで、その人が今何をしてるのか、みたいなメッセージが出てくるものですけど、この映画ではそれも無いんですよね。今も議員を続けてるのかも不明です。
別に、この点を批判とかするつもりは全く無いんですけど、ただ、チャーリー・ウィルソンという人間を描くのがメインという内容の映画だった方が、私は楽しめたような気がします。その方が、トム・ハンクスの活躍度ももっと増していたはずだと思うんですよね。多分ですけど、この映画を見に行く人の大半は、トム・ハンクスを見に行ってるんだと思いますし。でも、この内容だと、「トム・ハンクスが朗読する、近年のアメリカの歴史」を聞いてるような気がして、あんまり、「ハンクスの演技を堪能した」という面白味が感じられないんですよね。
先月、クルーズの方のトムが出演している、同じく「最近のアメリカの問題」を語っていた社会派映画の『大いなる陰謀』という映画が公開されてましたけど、時期が近いせいか、つい2作を比べて見てしまいます。で、あちらは映画としての面白味がありましたし(世間では『大いなる陰謀』の方が映画としての面白味が無いという意見が多いようですが・笑)、演技面の見所というのもあったんで、何だか、『チャーリー~』の方が印象が薄くなってしまいそうです。
スパイダーウィックの謎
<THE SPIDERWICK CHRONICLES>
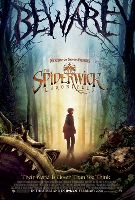
◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★☆
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★☆☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★★☆☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★☆☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★★☆☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★☆☆☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★☆☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★★☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 27点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
ヒットシリーズ以外は完全に飽きられてる感のあるファンタジー物で、私ももうこのジャンルに対する興味もかなり薄れてきているんですが、何故かこの映画は結構前から期待していたんですよね。
まず、舞台が異世界ではなく、現実世界を舞台にしながら魔物みたいなのが出てくるというお話であり、そこで少年少女のアドベンチャーが繰り広げられる、という内容に惹かれるものがあったのです。別に、こういうお話が特別好きというわけではないんで、自分でもなんでそんなに楽しみにしていたのかよく分からないんですけど(笑)。ただ、日記コーナーでも書きましたが、この映画の持つ「子供が見たら楽しいだろうな」という雰囲気が、どこか、私が子供の頃に見て熱狂した『グーニーズ』(映画館で見た初の洋画)を想起させるんですよね。もちろん、ストーリーもジャンルも全然違うものですけど、「子供向けで子供が主役のアドベンチャー」という辺りにはまあ似通っている点もありますしね。
で、実際見てみたら、期待していた通り、「もし私が子供の時に見たら熱狂しただろうな」と思えるような内容で、大変満足でした。ただ、『グーニーズ』よりは、私が映画館で見た2本目の洋画である『ウィロー』を見た時の感覚の方が近かったかも(こっちも面白かったですが、『グーニーズ』の方が面白かった)。映画の雰囲気自体は、どちらかと言うと『ウィロー』の方が近かったですしね。ジャンルも同じファンタジー映画ですし。
で、この映画のどういう所が面白かったかという話ですが、まず、主役のハイモア少年に、その双子の弟のハイモア少年(二役)、そして姉の3人がメインキャラなんですが、それぞれ得意分野や性格分けがかなり分かりやすくされているのがいいですね。サブキャラのクリーチャーも面白いキャラクターでしたし。
対する敵も、小型で攻撃力もあまり高くなさそうという、弱っちぃ連中から始まって、中盤ではかなりのスピードで襲ってくる巨大モンスターが登場し、ラストには『ロード・オブ・ザ・リング』や『ナルニア』の中ボスとして出てきてもおかしくないような手強いのが登場してきます。最初の小型の連中ならともかく、デカキャラ軍団はとても子供が相手に出来るとは思えないような奴らなんで、そういった敵の襲撃シーンは中々迫力がありましたね。特に、ラスボスは結構な大暴れを見せてくれて、ほんと、子供の時に見たら、ホラー映画で出てくるモンスターを見るのと同じぐらいの恐怖を味わっていたかもしれません。
でも、主人公の少年が、そういうクリーチャー達を相手にしていても、あまり恐れを見せていないという辺りはかなり頼もしさを感じましたね。「コイツならなんとかしてくれそうだ」という安心感があるぐらいです。
ついでに、当初は「コイツ、絶対、後にグレる事になるな」と思われるようなキャラクターだったのが、ストーリーが進むごとに段々と精神的に成長していってるのが感じられるのも面白い点でした。
最終的には、家族みんなのリーダーとなって(父親は不在ですが)、敵との戦いを指揮するぐらいになっていくというレベルアップぶりです。
そんなキャラクターを、見てて違和感を持たせずに演じていたフレディ・ハイモアは、まあ、さすが名子役といったところですかね。
あと、家の周りだけで完結するような狭い範囲の話かと思ったら、ちょっと遠くの町に遠征する場面があったり、妖精の国みたいな所に行くシーンがあったりと、思っていたよりも広がりのある話だったのも良かったですね。
地理的な広がりだけではなく、スパイダーウィック家の数代前の時代から始まっていた長いストーリーだったというのも、何か壮大な感じがしていいです。そして、その全てに決着がついたラストは結構感動的でした。
と言うわけで、久々に童心に戻って楽しめる(まあ、こちらから無理して童心に戻ったみたいな面はあったものの・笑)、楽しい映画でした。
ミスト
<THE MIST>
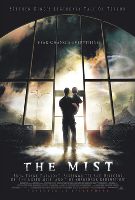
◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★★
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★★☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★★★☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★★☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★★☆☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★★★☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★★☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★★☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ★☆☆☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 35点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
まあ、怖い映画でした。原作を読んでいなかったんで、どういう内容なのかは映画の宣伝から得た情報しかなかったんですが、それによると「霧の中に何かがいる」「閉じ込められた人達の間でいさかいが起こる」といった、どう転んでも地味になりそうな内容ですよ。でも、公開からわずか数日で各地で高い評価を得てるのを目にしていたので、「いったい、どんな映画なんだ」と思っていたんですが、なるほど、これは確かに凄い映画です。
『ショーシャンクの空に』『グリーンマイル』と、キング原作映画を続けて成功させたフランク・ダラボンですが、今回は失敗する事が多いとされるホラー系の映画です。「これまでダラボンが成功してきたのは、ドラマ系の原作を選んでいたからなのでは」と思っていたのですが、見事にホラー系でも傑作を撮り上げてしまいました。『ドリームキャッチャー』もこの人が撮ったら全然違う印象の映画になったのかもしれないですねぇ。
まず、霧の中にいる「何か」が怖かったですね。あんなのが出てくるとは全く予想してませんでした。だいたい、映画で「霧の中に何かがいる」という設定が出てきたら、もう無意識に「幽霊がいるんだろう」と思ってしまうんで、今回もそんなようなのが時々出てくるだけなんだろうと高をくくっていたんで、あんなのが出てきたのを見た時は本気でビビってしまいました。
しかもこの霧が、「中に何かがいる」という段階じゃなくって、もう、霧の向こうの世界がどうなってるのかすら分からないぐらいの圧迫感があるものなんですよね。もしかしたら、霧の中は地獄か何かになってしまっているんじゃないかと思わせるような・・・。
で、その霧から逃れる為にスーパーマーケットに篭城するわけですけど、この、「外の世界を跋扈する何かから逃れる為に建物に閉じこもる」というのは大好きな設定です。この閉じこもった人々の間の人間模様も中々興味深いものでした。
そして、当然のように「協力し合わない」とか「諍いが生じる」といった展開になっていくんですが、この辺り、映画を評価する観点で見ると実に正しい人物描写だと思います。「本当に怖いのは人間の心の闇だ」みたいな。でも、私は生き残りが団結してサバイバルする話の方が好きです。こういう、みんなで助け合わなきゃならない時にいがみ合ってるのを見てるとイライラしてきます。だいたい、「本当に怖いのは人間の方だ!」みたいな事は、今更説かれなくても分かってる事ですからね。
なので、最近の『ドーン・オブ・ザ・デッド』だとか『ポセイドン』だとかで、生き残りの間であまり摩擦が起こらない人間ドラマが描かれるというのは個人的にいい流れだと、正直思ってました。映画ファンや評論家にとっては面白くない展開なんでしょうけど(笑)。
なので、この映画の篭城場面でも時々イライラする箇所があったりしました。何しろ、一人大変ムカつく奴が紛れてましたからねぇ。「コイツ、いらねぇよ」と何度思った事か。もちろん、映画のテーマ的な面でも必要な人材だというのは分かるんですが。
でも、この映画は心理ドラマだけの映画ではなくって、怖いのが出てきて人が残酷に死んだりする見世物系ホラー映画としても大変よく出来てるんです。先にも書いた、私の予想の範囲外だった「霧の中の何か」がもう、大活躍してくれるんですよ。それこそ、「もし、自分がこの世界にいたら」と妄想するのが嫌なぐらいに恐ろしい事態が劇中で巻き起こってくれてるんです。『アイ・アム・レジェンド』の感想でも同じような事を書きましたけど、この『ミスト』の世界の方が「サバイバルしたくない度」ははるかに上ですね。あの「霧の中の何か」に襲われるよりは、ゾンビもどきに襲われた方がまだマシです。
そして、こういうホラーな展開を、出来る限りリアルに見せるような演出がされてるんですよね。まず、何事も起こる前の、序盤の辺りのシーンというのが、アメリカの田舎町の日常をそのまま見てるみたいな、妙に臨場感のある雰囲気になっているんです。日常と言っても、大型の台風が過ぎ去った後の、混乱が残ってる状況での日常ですけどね。でも、もし今晩私の住んでる地域に大型台風が来たら、明日はウチもこんな感じになるんじゃないかと思うような、ごく当たり前の“日常”というのを感じさせる演出になっていました。
そして、その雰囲気のままで霧が登場し、一気に異常な世界に突入していくんです。この序盤の日常の描写があるからこそ、この異常事態に対するストレスのようなものがより強く感じられるんですよね。この霧を抜けて、元の生活に戻りたいと思うんですけど、霧は依然としてそこにいるままですし、中を突っ切ろうとすると大変な目に遭うわけですよ。
あとは、この状況を登場人物がどう切り抜けるのか、というのが見たくなってきます。で、これまで殺人ザメや宇宙怪物、トラボルタといった強敵と戦ってきた我らがトーマス・ジェーンが(トラボルタと戦ったのはトム・ジェーンだったか・笑)、生き残り達の間でリーダーシップを見せてみんなを引っ張っていくんですが、そこに、宗教家のオバチャンが割って入ってきて、厄介な事になっていくわけですよ。こいつさえいなければ、みんなをまとめあげられたかもしれなかったのに。それにしても、ほんと宗教というのは厄介な存在ですねぇ。どうにかならんものか。
ラストが原作と変えられているというのが話題でしたけど、多分、原作通りのラストだったら、「怖くて面白いけど、少し引っかかるものが残った映画」という印象に落ち着いたような気がします。
ですが、この変更されたラストというのがまた大変なもので。もう各地で「衝撃的」と言われていますけど、本当に凄いんですよ。
「ラストが衝撃的」という情報が鑑賞前に入っていたんで、その前情報プラス、劇中に終盤の展開を匂わせるヒントが2回ほど出てきていたというところから、「どういうラストになるのか」というのは、一応、予想がついていたんです。でも、“予想”と“実際に目にする”のとでは衝撃度はやっぱり全然違いますからね。もう、映画が終わった瞬間、頭を抱えて絶叫したくなってしまいましたよ。それぐらいの衝撃があるラストでした。
そして、このラストで映画の印象もかなり変わってきました。まあ、要するにバッドエンドなんですけど、「主人公が死んで終わる」みたいな、よく見る中途半端なバッドエンドじゃないんですよね。それだと「見終わった後、鬱になる」みたいな印象が残るだけなんですけど、この映画はもう、「これが真の絶望というものぞ!」みたいな、かなり突き抜けた感があるんで、むしろ「よくやったなぁ」と感心するぐらいなんですよね。「なんて凄い事をやらかした映画なんだろう」と、凹みながらも思ったものでした。
(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください
紀元前1万年
<10,000 B.C.>
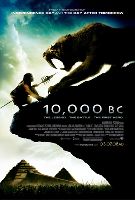
◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★☆☆
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★☆☆☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★★★☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★☆☆☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★★☆☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★★☆☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★★☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★☆☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 26点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
待望のローランド・エメリッヒ監督最新作ですが、どうも、あんまり期待感の沸かない映画でした。紀元前1万年の世界なんて、あまりに昔過ぎて、そこで巻き起こるストーリーというものに興味が持てなかったんですよね。他の時代物の映画やファンタジー物映画よりもさらに地味になるんじゃないかと。それに、原始人が主人公というのもちょっとピンとこない点でした。
でも、見てみたら、さすがエメリッヒだけあって、それなりに派手で面白い内容にはなっていました。「人類最初の英雄物語」といった趣のストーリー展開も良かったです。
それに、時代考証に関してあまりこだわってないのか、『アポカリプト』辺りの年代が舞台の映画とそれほど変わらないような印象でした。主人公も原始人っぽくなかったですしね(しかも、古代マヤ人よりもファッションに気を使ってそうな衣装でしたし・笑)。
でも、そうなると時代設定を紀元前1万年にする理由は何かあったんだろうかとも思うんですが、監督のインタビューを見る限り、「マンモスを出したかったから」みたいな理由っぽいですね。確かに、『アポカリプト』には、巨大生物は出てこなかったわけですし、「猛獣ではなく、巨大生物が襲ってくる時代物映画」と考えれば、この時代設定も面白い試みだったのかもと思えてきます。
ただ、それならそれで、『ジュラシック・パークⅢ』並みに、古代の巨大生物がガンガン襲ってくるような見せ場があっても良かったかなとも思うんですよね。結局、出てきたのはマンモスとサーベルタイガーと、名前忘れましたが、デカくて凶暴なガチョウみたいなやつの3種だけでしたし、しかも、中でも最もボスキャラっぽい雰囲気のサーベルタイガーはほんのゲスト出演程度の出番しかありませんでした。
「マンモスや怪鳥といった巨大生物に槍一本で挑む」というアクションシーンは割と面白い映像だったんで、こういう派手な見せ場がもっと欲しかったですね。
と、アクション面が見せ場不足という感じだったんですが、ストーリーの方は割と面白いものでした。
物語自体は『インデペンデンス・デイ』ぐらいの尺で語ってもよさそうな、壮大な感じのものなんですけど、ストーリー展開がかなり駆け足気味で、細かい部分を相当切ってるような編集になってるんです。「長い原作の映画を無理やり2時間以内にまとめあげた」系の映画みたいな圧縮感があったんですが、このストーリーをアクションシーン無しで引き伸ばしても退屈な映画になるだけだと思うんで(爆)、これぐらいテンポの早い展開でちょうど良かったです。
そして、ストーリーの中に、個人的に「これは面白い」と思える所があったんです。面白いと言っても、「興味深い」という方向の“面白い”ですけど、どうもこの映画、根底に「宗教というものに対する批判」のようなものが流れてるように思えるんですよね。
まず、この映画で敵として出てくる集団が、なんらかの神を崇めてる宗教団体なわけなんですが、こいつらは悪の帝国を築こうと(本人達は、自分らが“悪”だなんて思ってもいないんでしょうけど)、各地から人をさらっては奴隷として働かせ、でっかい建造物をおっ建てようとしているんです。
で、主人公達はそこに殴りこみをかけて、建造を阻止してしまうんです。元々の主人公の目的は「愛する人の救出」だったんですが、いつしか、英雄として仲間を率いて、悪の帝国を滅ぼして奴隷を解放する、みたいな展開になっていくんですよね。
造られていたのはピラミッドだったんですが、きっと、これが完成したら、ここで連中の大好きな“いけにえの儀式”とかが行われ始めて、何万という罪の無い人が殺される事になったんでしょう。『アポカリプト』でも描かれてた蛮行ですが、こういう恐ろしい事態が起こるのを止める事が出来たわけで、何だか胸の空く思いがしたものでした。
自分を“神”だとのたまってる敵のボスのあっけない最期といい、「もう、こういう胡散臭い奴の言う事なんて聞くな」というメッセージが感じられるようです。だいたい、本物の「救世主」とか「予言の子」みたいな存在は、奴隷を従えたり人を殺したりとかしないものなんですから。
ところで、“救世主”と言えば、主人公ではなく、ヒロインの方が後の救世主(1万年後に現れる予定のあの人)っぽい道を辿ってるのも面白い点でしたね。
そして、その悪の軍団を叩きのめしたのが、色んな部族が協力して出来た連合軍だというのも面白いです。一つの巨大な敵の前に人類が力を合わせるというのは、『インデペンデンス・デイ』でも出てきた展開ですが、今回はその敵が宇宙人から宗教になったようです。で、私も宗教は大嫌いなんで、この終盤の主人公の活躍には、見た目以上に燃えるものが感じられましたね。
とはいえ、神を崇める事自体は悪い事ではないんですよね。主人公も、“お告げ”というスピリチュアルなものを信じているようですし(ただ、村を出て行った父親は現実主義者だったようですが)、仲間になる各部族も、それぞれに信奉してる神がいたりするんでしょう。要は、「それが、他人に害をなすものかどうか」という事なんですよね。
でも、実は「本当にエメリッヒは宗教批判なんてメッセージを込めてるんだろうか?」という気もします。私が宗教嫌いだから、先入観か何かでそう読み取ってしまっただけなのかもしれません。でも、映画なんて、どう解釈しようが観客の自由みたいな意見もある事ですし、私自身、この解釈で楽しめたわけですから、これでいいんでしょう。
NEXT -ネクスト-
<NEXT>

◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★☆
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★★☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★☆☆☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★★☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★☆☆☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★★★☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★☆☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★★☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ★☆☆☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 30点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
「2分先の未来が見える」という能力を持った男の話で、原作はあのフィリップ・K・ディックです。でも、ディック原作映画にしては、SFっぽさが全然無かったですね。超能力物とかヒーロー物っぽい雰囲気でした(唯一、「目を開けっ放しにさせておく道具」の造形が、何かディック原作映画っぽかったですけど・笑)。
それにしても、いくら未来が見えるとはいえ、たったの2分では大した役に立たないんじゃないんだろうか、と見る前は思ってました。しかも、ストーリーの最終的な目的が「テロリストが国内に持ち込んだ核爆弾を探す」というものです。これって、「2分先が読める超能力者」じゃなくて、「テロ対策ユニット」にやらせるべき仕事なんじゃないんだろうか。
でも、だからこそ、ストーリーに対する興味が湧いてくるんですよね。2分先が読める能力をどう活かしたら核爆発を阻止出来るのかと。ただ、なぜ、FBIが2分先を読む能力を持つ男を欲しがっているのかはよく分からなかったんですが(捜査の役に立つとは思えないですし)、まあ、この手の娯楽映画ではそういう、「強引な展開」というのが出てくる事も時々あるんで、おとなしくスルーしておくのが正解なのでしょう(笑)。
で、この能力ですが、意外にも、アクションーンにおいて相当有効な能力だったんですよね。もし、『X-MEN』にこの能力を持ってるミュータントがいたら、ウルヴァリンは勝てるんだろうかと思うぐらいに強力な能力だったんです。
実は、「次に起こる事」というのを、ほんの一瞬で思い描く事が出来るようで、ケンカの時に相手のパンチを「相手の方を見ないでかわす」といった事が出来たり(どの角度からパンチが飛んでくるのかが分かるので)、遠くからの狙撃でさえも、「どこから弾が来るのか」というのが分かるので避ける事が出来るんです。
もう、ほとんどニュータイプみたいになってましたからねぇ。この能力を駆使したアクションシーンは見ててかなりユニークで、印象に残る場面ばかりでした。冒頭の、「カジノから警備員に見つからないように脱出するシーン」もかなり面白かったですし、クライマックスの銃撃戦も最高でした。FBIとテロリストの銃撃戦が巻き起こってる最中、主人公は何の装備も無しに歩き回ったりしてるんですよね。そして、時には味方に敵の位置や罠の存在を教えたり、回避の指示を出したりとかするんです。いやはや、「2分先まで読める」というだけで、ここまで無敵になれるんですね。
そして、こういう、アクション場面のみに有効な能力というわけではなく、会話にも利用出来るんです。例えば、「どう話しかけたら相手の警戒を解けるのか」という際、色んなパターンを試して相手の反応をみてみた後、その中から正解が見つかったら、それを実際に話せばいいわけですからね。
いやぁ、実に夢のある能力でしたねぇ。『ジャンパー』を見た時も「羨ましい能力だ」と思いましたけど、もしかしたら、こっちの能力の方がいいかもしれません(両方使えたら最高なんですが・笑)。
で、この能力をどう活かして核爆発を阻止するのかという点ですが、ここはネタバレになるので詳しくは言えないんですが、どうも、やっぱり役に立ってなかったような気がするんですよね(笑)。敵の本拠地を見つけて、そこに襲撃をかける時なんかは有効な能力なんですが、やはり、捜査にはあまり向いてないようです。
まあ、映画自体は視覚的に大変面白いものだったので、特に文句は無いですけどね。ストーリー面の緻密さよりも面白さを優先している映画の方がやっぱり有り難いなと思えます(両方備わってるというのが一番望ましいんですけどね・笑)。
さて。そんな事よりも、私がこの映画で一番期待をしていた箇所は、主役を演じるのがニコラス・ケイジという点でした。ただでさえ、お世辞にも美形とは言えない面構えの人だというのに、今回のニコさんは「広い額が強調される髪形」なんてのをしていて、もう、パッと見、ただのキモいハゲオヤジにしか見えない有様になっているんです。もはや、主役の顔というより、脇役の顔みたいになってましたからね。それなのに、演じるのは超能力を持ったヒーローという辺りに、きっと何とも言えない魅力が醸し出される事になるのではないかと思っていたのですが、見てみたら、まさにその通りで、ただでさえ画期的なアクションシーンが、さらに映像的に面白い事になっていましたねぇ。
ジェシカ・ビールみたいな美女にモテたり、カッコいいポージングで弾丸やら落下してくる車やらを避けるというスーパーアクションを見せたりといった事、本来ならキアヌ・リーブス辺りが似合う事だと思うんですけど、それを敢えてニコラス・ケイジがやっているという、このミスマッチ感が何かたまらなく面白かったですね。
でも、やっぱり演技力には定評のある男だけあって、動きや表情にどこか華があるのが感じられるんですよね。「ただのハゲではない」という存在感があって、超能力を駆使するヒーローをしっかり、魅力的に演じているんです。いやぁ、さすがですねぇ。
(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください
クローバーフィールド/HAKAISHA
<CLOVERFIELD>

◎満足度 ★★★★★
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★★
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★★☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★★★☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★☆☆☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★☆☆☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★★★☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★★☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★★★
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ★★★☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 35点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
全米公開時、どんな内容の映画なのかを伏せられていたんですが、その正体は「ニューヨークに怪獣が現れて町を破壊する」という映画でした。でも、この映画が怪獣映画であるという前提を知ってるのと知らないのとで、どっちがこの映画をより楽しめるんだろうと思った時、どうも、「知ってた方が楽しめる」という気がするんですよね。むしろ、知らないで見ていたら、怪獣が出てきた所で「何だ、怪獣映画かよ」とガッカリされてしまうのではないかと(怪獣映画が好きな人ならいいんですけど)。
あと、「全編、手持ちカメラによる主観映像で撮る」という手法により、画面が終始揺れまくるという情報も、広く開示しておいた方がいい事ですよね。もしこれを知らずに、前の方の座席(真ん中でも危ないかも)を選んでしまったら、もはや映画を楽しむどころの話じゃなくなると思いますからね。
で、この「知っておいた方がいい2大情報」を得たうえで、「映画の楽しみどころはどこなのか」「酔わない為にはどうすればいいのか」という対策をしっかり講じてから臨んだのが良かったのか、もう、大満足させてもらう事が出来ました。ほんと、もうあまりに面白くて感動するぐらいでしたからね。
あと、「怪獣映画ファンによると傑作らしい」という情報が入ってきていたので、「そのジャンルの中でレベルが高い映画だ」という前提が見る前から出来ていたのも良かったのかもしれません。
ところで、ハリウッドの怪獣映画と言えば、ちょうど10年前に『GOZZILA』という映画が公開になりましたけど、実は、あの映画とかなり内容に似た所があったんですよね。「これ、リメイクだったっけ?」と思うぐらいでしたよ。
でも、『GOZZILA』は評判のあまり良くない映画だったんで(私にとってもイマイチな映画でしたし)、もしかしたらリメイクと言うよりリベンジという意味合いのある映画だったりするのかもしれないですね。それにしても、ハリウッドの怪獣映画は10年でこんなに進歩したんですねぇ。技術的には、10年前でも作れそうな映画だったんですけど(笑)。
さて。「手持ちカメラの目線で全てを見せる」という演出で押してくる映画ですが、これは中々面白い手法だったと思いますね。過去にも同タイプの手法を使った映画はありましたけど、ジャンルが違うせいか、結構新鮮な感覚すらありました。
特に、背景から「オーマイガー!」の連発が聞こえてくる辺りのリアル感は、パニック映画とかでもあまり無かった点かもしれません。もう、聞いてるだけで「ああ、とんでもない事態が起こったんだな」と思えてきます(ちなみに、日本人の場合は、例えば奈良の大仏の首が飛んできたりとかしたら何て叫ぶんだろう。「ワー!」とか「キャー!」辺りになるんだろうか)。
ただ、この主観撮影という手法により臨場感というのが増して感じられたのか、というと、実はそうでもなかったんですよね。むしろ、「撮影者」というのを感じさせないドキュメンタリータッチの演出というものの方が、臨場感や緊迫感は出せるんじゃないかと思います(ポール・グリーングラスの映画みたいに)。
それに、やっぱり「画面の揺れ」はかなりのものでしたからね。ほんと、映画館で座る席を間違えたら、健康を害する恐れもあるぐらいです。なるべくスクリーンから離れた位置から見て、さらに、会話メインのシーンでは、なるべく字幕に視点を合わせて、画面は「視界に入ってる」ぐらいの位置に入れておく見方をするといった工夫をして臨むのが最低条件ぐらいの揺れっぷりでした。
でも、実は、一番画面が揺れていたのは、多分、まだ何も事件の起こってない、序盤のパーティのシーンだったように思えるんです。まだ撮影者がカメラの扱いに慣れてないという事なのか、この辺りのシーンは相当揺れていたんですが、何しろ、画面を見てる必要もあまり無いぐらいのどうでもいいシーンなんで、ここを上記の「字幕に視点を合わせ、画面は視界の端に入れておく」という見方でやり過ごすと、ダメージが蓄積されないせいか、後半で疲れないんですよね(ここをしっかり見てしまうと、中盤ぐらいでダウンするハメになるような気がします)。
で、この映画の凄い所は、怪獣の襲撃等の「肝心なシーン」というのを、隠さずに見せてくれるという点です。パーティが終わって、大パニックが起こるという、いわゆる本番が始まると、普通は、画面の揺れはもっと激しくなると思いますが、逆に、ここから揺れがあまり気にならなくなってくるんです。
もちろん、移動中の場面なんかは激しく揺れますけど、そういう所は、まあ別に画面が見づらくなってても特に問題無い場面じゃないですか。でも、「ここは画面をハッキリ見たい」と思うような場面では、ちゃんと画面の揺れが抑えられているんです。
本当にリアル感を出したいのなら、こういう場面でも激しく揺らさないといけないんでしょうけど、この映画の監督(及び製作者)は、リアルさよりも見易さをとったんです。これはもう、「大正解だ!」と声を大にして言いたいですね。「臨場感を出す為」という事で、アクションシーンで急にカメラをブレさせてくる映画が最近多い事を考えると、その流れに一石を投じる手法なんじゃないかと嬉しくなってくるぐらいです。だって、全編揺れててもおかしくない状況を作ってる映画なのに、本来一番揺れててもおかしくない場面を揺らしてないんですから。ハリウッドの映画人は全員見習って欲しいです。
このように、観客の見たい場面をちゃんと見せてくれる映画なんですが、この見せ方も考えられていて、だいたい、「一瞬だけ見える」みたいな感じになっているんですよね。こういう、想像力の刺激される見せ方をされると、見ててワクワクしてきます。
肝心の怪獣の姿も、この「一瞬見える」というのをずっと繰り返して、最後の最後にハッキリと画面に登場させるという、この出し惜しみの無い所も最高じゃないですか。その一方で、事件の全貌は一切伏せられてる辺りも面白いです。
ところで、上で、この映画のビデオカメラによる主観撮影という演出では、臨場感は思ったよりも感じられなかったというような事を書きましたが、この手法からはそれとはまた違う面白さが感じられるという効果が出ていたんです。
それは、「自分もその場にいるような感覚」ではなく、「事件の真っ只中に放りこまれた他人の悲劇を、ビデオカメラというフィルターを通して覗き見る」という感覚です。これは、普通の手法の映画では味わえない感覚だと思います。
あと、舞台がニューヨークという事で、どうしても「9.11」を思い出してしまうんですが、あの事件の「ツインタワーに飛行機が突っ込む映像を誰かが撮影していたビデオカメラの映像」から感じられた恐怖感、というのを出す事をこの映画は目指していたのではないんだろうかと思うんです。
撮影者がもはや生きていないという事を冒頭で明かすという事で、映画の主人公達が「いかにして最期を迎えるのか」というラストにするというのも、『ユナイテッド93』を思い出させますよね。
もう、9.11を経験した後だからこそ生まれ得た映画という感じなんですが、それにしても、あんな現実の大惨事を、娯楽映画の表現方法の「経験」にしてしまえるとは(まだ10年も経ってないのに)、アメリカ恐るべしです。
(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください
大いなる陰謀
<LIONS FOR LAMBS>
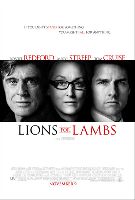
◎満足度 ★★★★☆
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★★★
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★★☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★★★☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★★★☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★☆☆☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★☆☆☆☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★☆☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★★☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 29点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
もう、見る前から「難しい映画に違いない」という予感のする映画でしたが、意外にも、最近の社会派映画の中でも、かなり分かり易くて見易い映画でしたね。『シリアナ』とかみたいに、「わざと分かりにくく描いてるのか」と思うような感じではなく、伝えたい事をしっかり伝えようとしてるように感じられる演出になってるんです。
映画は3つのパートから成り立っていて、それぞれ、「上院議員とジャーナリスト」「大学教授と学生」「兵士」といったキャラクター達の織り成すストーリー(ほとんど会話中心ですが)から、「現在のアメリカの抱えている問題」というのが語られる事となります。どこか一方からの目線ではなく、色んな目線から語られるというのが面白いですね。
「今のアメリカの問題」とは、即ち、イラク戦争関連です。で、「あの戦争は間違いだった」という前提で話は進んでいくんですが、戦争に賛成だった人は当時どういう事を思っていて、今はどう思っているのか。そして、マスコミは今まで何を伝え、何を伝えなかったのか、という話が出てきます。
そういった「現状の反省」だけが目的ではなく、ではこれからアメリカはどこに向かえばいいのかというのをみんなで考えていこう、というメッセージが発せられてるように思えましたね。
そして、次の時代を担う若者の政治不信についても言及していて、「次は君達が頑張って、政治を正しい方向に向かわせて欲しい」みたいなメッセージもあるのかもしれません。
こういったテーマをただ流すだけの映画ではなく、映画としての“面白味”というのもあるんですよね。映画全般を通して、対話シーンというのが多いんですけど、これが、ちょっとした論戦みたいな感じのやりとりになってるんです。で、これが見てて面白いんですよね。いかにも頭のいい人達の話し合いといった感じで、見てるこっちまで頭が良くなったような気になるぐらいです(アクション映画を見て、自分も強くなったような気になるのと同じような感じで・笑)。
特に、私はこういう「意見をぶつけ合う」みたいな事が苦手なので(そもそも、対話自体があまり得意ではないので・笑)、まるで超能力合戦を見てるかのような凄味が感じられましたね。話術があるとこんな高レベルの話し合いも出来るのかと感心したものでした。
あと、3大スターの共演というのもこの映画の話題の一つですが、やっぱり、皆さん上手いんですよね。「会話でメッセージを語る」という内容の映画ですが、この芸達者なスター達が、キャラクターに血を通わせたうえで語っているので、より身近な問題として受け止められるんですよね。ニュースキャスターが原稿を読むとか、識者が一人で語り倒すのとはまた違うメッセージの発信方法のように思えたものでした。
フィクサー
<MICHAEL CLAYTON>
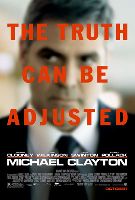
◎満足度 ★★★★☆
(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎評価度 ★★★☆☆
(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)
◎リピート度 ★★★☆☆
(今後、何回も見たいと思えたかどうか)
◎ストーリー ★★☆☆☆
(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)
◎キャスト ★★★☆☆
(キャスティングが良かったかどうか)
◎キャラクター ★★☆☆☆
(登場キャラクターの面白さ)
◎映像 ★★☆☆☆
(映像がどれぐらい凄かったか)
◎音楽 ★★☆☆☆
(音楽が印象的だったかどうか)
◎期待度 ★★★☆☆
(見る前の期待に応えてくれたかどうか)
◎ボーナス点 ★☆☆☆☆
(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)
合計 25点 (50点満点中)
 <個人的感想>
<個人的感想>
ポスターやチラシ、予告などから、「小難しい内容でストーリーにはついていけないが、クルーニーの渋い魅力の前に、見ててシビれたりするような映画に違いない」と期待していたんですが、見てみたらまさにそのままの内容で、大変満足でした。
一応、ストーリー展開に関しても、サスペンス面の流れにはついていく事が出来たんで、『グッド・シェパード』みたいに「何が言いたい映画なのかさっぱり」という状態にはならずにすみました。
でも、やっぱり、所々分からない箇所があったり、主人公の心理面を描写してると思われるシーンで、何を訴えようとしてるのかを掴みきれなかったりという面もあったりしましたね。特に、「馬に見とれたおかげで命拾いした」なんてシーン、もう、どう解釈したらいいのかてんで分からない展開でしたからね。なんとなく神秘的な雰囲気は感じられましたけど。
なので、主演がスター俳優じゃなかたら「ただ地味な映画」という印象で終わったのかもしけませんが、結局、ハリウッドを代表するダンディズム・スターが主演だったので、何の問題もありませんでした。
でも、思っていた以上に地味なストーリーだとも思いましたね。大手製薬会社の訴訟問題というのが背景にあって、主人公の役どころが「揉み消し屋」。というわけで、どんな裏工作をしでかしてくるのかと思っていたら、実は、主人公の心理描写的な面がメインに描かれるタイプの映画なんですよね。それに、どうも、主人公があまり揉み消しの仕事をしてるシーンというのが無いんで、何だか、「主人公が終始困ってるだけ」みたいな感じになってました。
でも、この「悩むクルーニー」というのが、また絵になるんですよねぇ。プライベートの問題にも悩まされたりするんですが、それが、よくある男女間のゴタゴタとかではなく、自身のギャンブル癖や投資への失敗から膨らんでいった借金問題というのがいいんですよね。これこそ大人の悩みだとか思います。なぜそう思うのかは私もよく分からないんですが。
それにこの映画、クルーニー度が相当高いんですよ。まず、マイナスに思えるような要素が無いんですよね。例えば『シリアナ』みたいにヒゲ面じゃないですし(あれはあれで、ワイルドな感じがあって良かったですけど)、『グッドナイト&グッドラック』や『さらば、ベルリン』みたいにモノクロ映像でもありません。『ソラリス』みたいにケツを出してきたりもしませんし、『ディボーズ・ショウ』みたいに情けない役回りでもありませんでした。スーツでビシっとキメて、フルカラー映像のクッキリ鮮明な姿でスクリーンに現れ、しかも、ブラッド・ピットがいないんで完全に独壇場状態です。まさにクルーニー劇場。
と言うわけで、「主演スターの魅力を愉しむ」という面では、文句無しの映画でした。これで、後に2回目、3回目を見た時、今回はイマイチよく分からなかったストーリーの細かい所や心理面などに理解が出てきたら、ますます面白く見られるようになるわけですよ。いやぁ、何てポテンシャルの高い映画なんだろう。
 ←前に戻る
←前に戻る
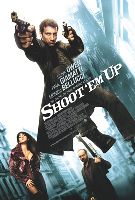 ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>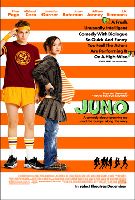 ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>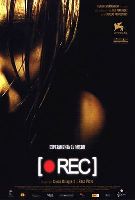 ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>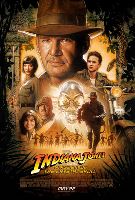 ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>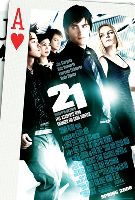 ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>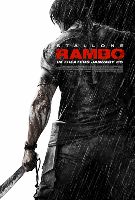 ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>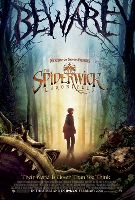 ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>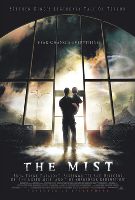 ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>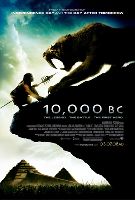 ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>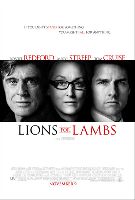 ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想>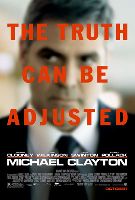 ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>
<個人的感想> ←前に戻る
←前に戻る