※点数は、独自の基準で弾き出したもので、その映画の「完成度」ではなく「どれぐらい好きか」を表しています。
 THE 4TH KIND フォース・カインド
THE 4TH KIND フォース・カインド
<THE FOURTH KIND>
個人的評価 22点 (50点満点中)
◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎肯定度 ★★★☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)
◎評価度 ★★☆☆☆ (客観的に評価してみる)
◎おススメ度 ★☆☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)
◎ミラ度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)
 <個人的感想>
<個人的感想>
予告を見た時は、『エクソシスト』のような悪魔系オカルト映画か、もしくは心霊系の映画なのかと思っていたんですが、まさか、異星人によるアブダクト系だったとは意外でしたね(そもそも、タイトルの“フォース・カインド”というのが異星人との接近遭遇に関する言葉だったようですけど・笑)。
で、私にとって、“悪魔”“心霊”“宇宙人”の中で、一番面白くないネタだと思うのが何を隠そう“宇宙人”なので、まあ、ガッカリしましたよ。
宇宙人でも、侵略目的で現れてるんならいいんですけど、誘拐目的は面白味が感じられないですねぇ。胡散臭いだけで。だいたい、もう10年以上前に『X−ファイル』でやり尽くしたネタを今更映画にしてどうするつもりだったんだろう。
このネタも、信奉者、懐疑論者どちらの視点でも見られるような中立の作りだったらまだ興味深く見られたと思うんですよ。例えば『エミリー・ローズ』なんかは、「悪魔は存在する」と「精神病が原因です」の、どちらとも解釈出来る内容になっていたんですけど、この映画は、完全に「異星人は存在しますね、間違いなく」というスタンスで語っているんですよね。でも、そのクセ、異星人やUFOがハッキリ姿を見せるという事は無いんです。こういうのを“中途半端”と言うんじゃないんだろうか。
この映画、「実際の事件を元にしている」という事になっていて、映画そのものが「再現映像」という形になっている事が冒頭で明言されていました。
で、実際に起こった事を録画した映像というのも出てきて、時には、俳優が演じる再現映像と実際に起こった記録映像を分割スクリーンで同時に見せてきたりといった演出も出てきました。
多分、『ブレア・ウィッチ〜』のようなニセドキュメンタリー物映画の変化球的な位置付けの作風という事になると思いますし、この手法自体は面白いものだったと思います。でも、何しろネタ自体が面白くないのではどうしようもないです。
さらに痛いのは、劇中で数少ない恐怖シーンのほぼ全てが予告で使われてしまっていたという事ですよ。驚かしのタイミングも、もうすでに予告で学習してしまっているんで、テレビスポットで見られたような「この映画を鑑賞中、ビックリシーンで飛び上がる観客」のようなリアクションをとる事も出来ません。
一応、多少ゾクっとはするような、いい映像ではあったんですけど、その恐怖シーン以外の場面が基本的に退屈で間延びした感じなので、もはや、ちょっといいシーンがあった程度ではどうしようもないぐらいの感じなんですよね。
ただ、この静かでしっとりとした語り口は、どこか日本のホラー映画のような味わいがあって、最初の頃は「いいかも」と思っていたんですよね。途中で飽きてきたのは、題材に興味が無かったからであって、もし異星人ではなく、心霊物の映画だったら、印象は大分変わっていたんじゃないと思います。ついでに言うと、異星人アブダクト物に興味のある人なら、もっとのめり込んで見られる映画なのかもしれません。
ですが、私にとっては、「何の為に、今、わざわざこんな映画を作ったのか」がさっぱり分からない映画、という印象でしたね。唯一、この映画の存在に価値を見出せる方法があるとしたら、それは、この話が本当に実話だった場合でしょうね。
 カールじいさんの空飛ぶ家
カールじいさんの空飛ぶ家
<UP>
個人的評価 44点 (50点満点中)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)
◎評価度 ★★★★★ (客観的に評価してみる)
◎おススメ度 ★★★★★ (他の人に勧めても大丈夫そうか)
◎ワン度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)
 <個人的感想>
<個人的感想>
世界最強のアニメーションスタジオ、ピクサーの最新作というで、もう内容の良さは保証されてるようなものですけど、実際見てみたら、予想通り、当たり前のように素晴らしい内容でした。あまりに当たり前過ぎて、逆に有り難味が全然感じられないぐらいです。いやぁ、何とも贅沢な話ですな。こんな高クオリティな映画が作られるのが当たり前に思ってしまえるなんて。
さて。安易な続編に頼らず、毎回、オリジナルストーリーの新作で勝負してきていますが(『トイ・ストーリー』だけはシリーズ化しましたけど、まあこれだけは例外という事で)、今回のお話も、老人が主人公だとか、家に大量の風船を付けて空を飛ぶといった、新鮮味があり、尚且つ、夢があって楽しい内容を考え出してきていました。
ただ、何故か毎回、どこか似通った感じの映画にはなるんですよね。ネタも違うし、監督も違う人なのに。今回も、前半、と言うか冒頭がセリフ無しのサイレントで展開する所なんて、『ウォーリー』みたいでしたしね。
そういう意味では、新しい設定を持って来る割に、映画に新鮮味があまり無かったりもするんですけど、とにかく、ストーリーや映像等、映画全体の質が高いんで、鑑賞中はそういう雑念の入る余地も無く、ただただ見入ってしまいますね。観客の感動させ方や燃やし方を心得てるとしか思えない、無駄の無い、見事な演出とストーリーテリングです。
「主人公が旅(冒険)に出て、経験を積んで成長していく」という大まかな流れというのは、まあよく見る展開ではありますけど、老人とメタボな少年が秘境アドベンチャーをするというのは面白い捻りでした。
空飛ぶ家の話という事で、空の場面も多々出てくるわけですけど、その設定を活かした高所でのアクションシーンというのも、かなり見応えがありました。相変わらず見せ方とかも上手いんで、映像の迫力もありましたし、ほんと、見ててワクワクさせられました。
毎度毎度、このレベルの映画を作ってくるピクサーには驚くばかりなんですけど、ただ、あまりに模範的過ぎる内容故に、表現できない部分というのがあるんですよね。まあ、例えば、暴力描写だとか、少々品の無い展開が出てきたりだとか、そういう、賛否両論が起こりかねない、荒っぽさが感じられるような面ですよ(まあ、今回、一瞬だけ流血騒ぎが起きましたけど・笑)。
で、実は、そういう、模範的ではないし、荒削りな所もあるけど、でも“力強さ”というのが感じられる映画、というものの方が私は好きだったりするんですよね。
なので、ピクサーの映画って、毎回素晴らしい作品を作ってきてくれるとは思うものの、「それ以上の何か」が感じられる事というのが無かったりもするんです。唯一、他のピクサー作品とはちょっと毛色の違う感じのあった『Mr.インクレディブル』が、ピクサーの中で一番好きな映画ですしね。
小さな子供も対象にしないといけないんで、この模範的路線がこのまま続いてもいいとは思いますけど、たまにはちょっと冒険して、「ピクサーっぽくない」と思ってしまうような映画も作って欲しいなとも思います。
あと、CG映像の技術面に関しても、毎回かなりのチャレンジをしていましたけど、今回、パッと見、特にリアル感が増したというような事を思えた箇所が無かったんですよね。むしろ、『ウォーリー』や『ボルト』の方が映像はキレイだったような気がするぐらいでした。
ただ、実は、あるキャラクターの造形や動きがかなり凝っていたんですよね。これ、予告編でも全然姿を見なかったですし、私もこういうのが出てくるとは全く予想して無かったという意外性のある存在なので、ネタバレ防止の為にここでそのキャラについて語らない方がいいんでしょうね。
でも、このキャラクターの造形というのが、この映画の中で一番攻めてる部分のようにも思えまして、後にこの映画を思い返した際、真っ先に思い浮かぶのが(と言うか、記憶に残っている箇所が)このキャラ群のような気がするぐらいです。
(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください
 イングロリアス・バスターズ
イングロリアス・バスターズ
<INGLOURIOUS BASTERDS>
個人的評価 33点 (50点満点中)
◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎肯定度 ★★★☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)
◎評価度 ★★★★★ (客観的に評価してみる)
◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)
◎会話度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)
 <個人的感想>
<個人的感想>
映画ファンにとっては超有名でメジャーな監督であるタランティーノですが、私にとってはそれほど馴染みが無い人だったりします。まず、あまり多くない監督作の中で、2作も未見がありますし(『レザボアドッグス』と『キルビルvol2』)、他の映画も一回見たっきりです。『デスプルーフ』以外はどれもそれなりに面白かったんですけど、「もう一度見たい」と思うほど好きにはなれない映画という感じでした。
そして、今度の新作は、上映時間が2時間半もあり、しかも予告を見てもあんまり面白そうに思えなかったという事で、見に行くのにかなり気が重かったんですよね。特に、前に見た『デスプルーフ』の印象が残っているのか、「あの、くだらないダベりを2時間半も聞かされるのか・・・」みたいな事を思ってしまいました。
「レンタル待ち」との間でかなり揺れたんですけど、「でも、ブラッド・ピットの主演作は出来れば押さえておきたいしな」というミーハー的興味によって見に行く事となったんですけど、そうしたらこれが、「タランティーノ映画の中で一番面白かったのでは」と思えるような内容になってるじゃないですか。
まず、今回は会話シーンが、ただ無駄に長くてつまらないだけのものではなく、緊張感が漲っている、意味と意義のある会話シーンになっていたんです。まあ、今思うと、過去の映画で会話シーンが本当に無駄でつまらないものだったのは『デスプルーフ』ぐらいだったような気もするんですけど、よっぽどあの映画の負の印象が強かったんでしょうね。
今回、対話をしている人物のどちらかが何かを隠していて、それがバレたらエラい事になるという状況での会話シーンがほとんどなので、「いかにして相手を騙すか」とか「いかに相手の嘘を見抜くか」みたいな駆け引きの要素が入り込んでいるんです。
話の途中には、例によって、あまり意味の無い部分というのも多く含まれているものの、その部分すらも、「もしうっかり変な事を言ってしまったらマズい」という空気が出ていて、気が抜けないんです。もう、全体に渡って、いい刺激と緊張が感じられる会話シーンなんですよね。まさに「映画の見所」になっているんです。
おかげで、長い上映時間にも限らず、ほとんどダレる箇所が無かったんですけど(全体を5つのチャプターとして区切って語っているというのも良かったのかも)、ただ、会話シーンの「本筋と関係無い部分」を削ぎ落としたら、多分100分前後で収まった映画なんじゃないかな、なんて事もちょっと思ってしまいました。タランティーノ映画で「会話シーンをカット」なんて、ジャッキー映画のカンフーシーンをカットするようなものなんですけどね。でも、時間の長い映画というのは、他の映画との2本立て鑑賞がスケジュール的にやりづらくなるとか、尿意対策をして臨まないとならないとかいった問題が出てくるんで、出来れば映画は2時間以内でキレイにまとめ上げて欲しいな、なんて。
さて。今年は『ディファイアンス』と『ワルキューレ』という、2本のナチス物映画を見ましたけど、『ディファイアンス』にあった「ナチスへの反撃」と、『ワルキューレ』にあった「ヒトラー暗殺計画」の両方を描いているんですよね。実に豪華じゃないですか。まさに、今年のナチス関連映画の集大成ですよ。
さらに、その2作にあった「実話が元」というのが無くなっているんで、好きなように話を展開させられるという強みもあるんですよね。『ワルキューレ』では、映画が始まる前からヒトラー暗殺が失敗に終わる事が分かってしまってましたけど、こちらはフィクションなんで、もしかしたら成功する可能性もあると思いながら見られるんです。
まあ『ワルキューレ』も、失敗すると分かっていてもドキドキさせられましたけど、やっぱり、どう話が転んでいくか分からない『イングロリアス〜』の方がより緊張感が高かったように思えました。
何よりも、上で書いたように、会話シーンでの緊張感の出し方が冴えまくってたのが効いてましたね。タランティーノ映画ではお馴染みの、「重要な役かと思ってたキャラがあっさり死んだりする」という技も出てきますし、先の展開が予測出来そうで出来ないみたいな感じで、最後までストーリーに対する興味が持続していくんです。
「ナチスへの反撃」の面もかなり力が入っていましたね。と言っても、アクション面ではなく、残酷面ですけど(笑)。
ナチスと言えば、同情の余地の無い完全な悪役ですからね。何人殺しても、どんな手段で殺しても、誰の良心も痛まないという、生きた人間の中では虫けら扱いが唯一許される集団ですよ。もはや、ゾンビや巨大昆虫なんかと同じカテゴリーですね。
で、この映画自体が、残酷描写を笑って楽しむ系の映画として作られているんで、バスターズがナチスを狩り殺す様を拍手喝采して見ていいわけですよ。「思い知ったか、この外道どもめ!」と。何か、『シンドラーのリスト』と続けて見たら楽しい事になりそうな気もしてくるぐらいです。
ですが、何故かラストの方に、ナチス達が「ナチスの英雄が、敵兵を狙撃して殺しまくる映画」というのを、拍手喝采しながら見ている場面というのが出てくるんですよね。なので、「あれ、さっきのナチス虐殺シーンは笑ってみたらいけない場面だったのかな?」とか思ってしまいました。まるで「あの場面を見て喜んでるなんて、やってる事はナチスと一緒だよ」とか言われてるみたいじゃないですか。
多分、タランティーノにはそういう意図は無いと思うんですけど、やっぱり、この二つは関連付けて見てしまいますよね。どういうスタンスで見たらよかったんだと思ってしまいますが、「劇中で誰が死のうが、娯楽として楽しめ」ってスタンスで見ろという事のような気もします(笑)。
 インフォーマント!
インフォーマント!
<THE INFORMANT!>
個人的評価 27点 (50点満点中)
◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎肯定度 ★★★☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)
◎評価度 ★★★★☆ (客観的に評価してみる)
◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)
◎嘘つきは泥棒の始まり度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)
 <個人的感想>
<個人的感想>
実話を基にした詐欺師の映画という事で、見ていて『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』を思い出してしまいました(今回は詐欺師の自覚が無い人の話でしたが)。ですが、映画の「見易さ」に関しては段違いでしたね。もちろん、『キャッチ・ミー〜』が見易い方です。
多分、スピルさんの方は、エンターテイメント映画として、きちんと話が分かり易いように作っていたと思うんです。それに対して、同じスティーブンでも、この『インフォーマント』のソダーバーグの方は、芸術志向が高いのか何なのか知らないですけど、ストーリーテリングよりも雰囲気重視みたいな感じの語り口なんですよね。
ただでさえ混乱気味のストーリーだというのに、「観客に知らせるべき情報」が小出しにされてるように思えたり、本来ならあのシーンとこのシーンの間にあって然るべき説明シーンを敢えて省いていたりといった小細工を連発していて、何だか、無駄にややこしくなってる感がありまくりでした。
例えば、チラシや予告編等の情報から、この映画の主人公、マット・デイモン演じるマーク・ウィテカーという男が嘘つきのお調子者だという事は分かっていて、当初持ち上がっていた、「日本人スパイ」の問題がでっちあげだという事も分かっていたんですけど、映画では、この件が嘘なのか本当なのかをぼかしたままで話を進めていってるんですよね。なので、どういう態度で見ていったらいいのかが分からなくて、戸惑ってしまいましたよ。ウィテカーが嘘つきだというのを前提として見てしまっていいのか、それとも、後に「実は嘘だったんです!」という種明かしシーンがくるのに備えて、他の登場人物同様、ウィテカーを信じながら見ていた方がいいのか。
ウィテカーに虚言癖があるというのが、段々と判明していくという流れにはなっていて、最終的には「それも嘘なのかよ!」なんて方向にも話は広がって行くんですけど、その点がぼかされてる間は、ウィテカーが何を目的として動いているのかがよく分からないんです。
いや、「そういう話の映画だ」というのは分かるんです。でも、何か、回り道をさせられてるみたいな感じがしてしまったんですよね。例えば、『ニュースの天才』も同じような展開の映画でしたけど、あちらにはそういうモヤモヤは無かったと思うんです。ストーリーを無駄にややこしくしてるせいで、本来なら感じられたはずのストーリーの面白さが失われてしまってるような感じすらするぐらいでした。
結局、肝心の「価格協定の陰謀」というのが、本当にあったのか、それとも、これもデッチ上げだったのか、というのもよく分からなかったですしね。これだけは本当だったと思っていいんだろうか。
という訳で、見てる間は「しっくりこない感」というのがあったんですけど、今思い返してみると、このマーク・ウィテカーという男が「何を考えていたのか分からない、変な奴」というのを映画全体で描いていたのかな、という気がしてきました。この映画も、「何がしたいのか分からない、変な映画」という印象でしたからね。でも、どちらも共通して、「どこか憎めないユニークさ」というのがあるんです。
変に小難しい話に惑わされて、この映画がどういう映画なのかが中々見えませんでしたけど、この映画の登場人物も、ウィテカーの嘘にさんざん惑わされていたんですよね。
見てる最中は色々と文句が多かった割に、見終わった後の満足度がそれほど低くなくて、「おや?」とは思っていたんですが、なるほど、最後まで見ればこの映画の面白さと凄さがきちんと分かるような構成になっていたという事なんですね。
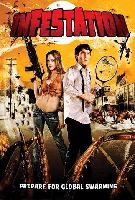 ビッグ・バグズ・パニック
ビッグ・バグズ・パニック
<INFESTATION>
個人的評価 41点 (50点満点中)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)
◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)
◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)
◎この映画、ムシ出来ない!度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)
 <個人的感想>
<個人的感想>
「巨大な虫が大挙して現れて人を襲う様をコメディタッタで描いたパニック映画」という内容ですが、もう、この紹介文を見ただけで血が騒いできますよね。何しろ、このジャンルには『スパイダー・パニック』やら『モスキート』等といった傑作がいますからねぇ。
で、この映画もそういった過去の良作の例に漏れない、イカした映画となっていて、大満足でした。
ただ、映画全体の雰囲気は、これまでの虫系パニック映画よりも、どちらかと言うと『ショーン・オブ・ザ・デッド』に近かったような気もしましたね。映画全体の雰囲気に、あの映画を参考にしてるような雰囲気が感じられたものでした。
当初は、どこかお気楽なムードが漂っていて、人が襲われたり死んだりするにも関わらず、それほど深刻さというのが感じられない、コメディ調の雰囲気なんですけど、終盤に向かうにつれて段々と真面目な雰囲気になっていくという流れを見せてくる所も共通ですしね。
それに、虫の「突き刺し攻撃」を食らった人が、後に、虫と同化したクリーチャーに変化してしまうというのも、「ゾンビに噛まれた人もゾンビに!」と似たような設定ですし、しっかり、「登場人物の知り合いや、かつての仲間等がクリーチャーと化して襲ってくる」という展開も出てきました。
さて。何かの生き物が巨大化して襲ってくる映画は、たいがい、その原因となるものも描かれるものです。まあ、だいたい核廃棄物だとか化学実験だとか宇宙からの隕石だとか、お決まりのパターンではあるんですけど、「これが原因で、こう広まりました」というのは前半で多少の尺を使って語られるものじゃないですか。
それが、この映画では、映画が始まってかなり早い段階、それこそ、まだ登場人物の紹介の途中かと思っていた辺りで急に巨大虫がはびこる世界に様変わりするんですよね。思わず「早っ!」と呟いてしまいそうになるぐらいでした。
結局、最後まで何が原因でこうなったのかがよく分からないままなんですけど、でも、この映画を「見たい」と思ってる人にとっては、多分、虫の巨大化の原因とか広まる原因とか、もうどうでもいいですよね(笑)。むしろ、余分な面が省かれてて、見易く感じられたぐらいです。
そして、この手のパニック映画の楽しみ所の一つとして、「もし自分がこの世界にいたら、どうサバイバルするだろうと考えてみる」というのがありますけど、この映画は結構、サバイバルし易そうなんですよね。
基本的に、大きな音を立てなければ襲われないんで、移動も割と楽だったりしますし、何よりも、思ったよりも数が多くないんです。まあ、多分、予算の関係なんでしょうけど(笑)、虫の数どころか、虫の襲撃シーンすら、予告で見たのでほとんどという有様でした。
確かに、外見はちょっとアレな連中ですけど、どことなくチープで、作り物っぽい感じがする造形なせいか、他の映画で見る巨大虫よりは、おぞましさが若干控え目な感じなんですよね。
肝心の虫の造形がチープなうえ、合成もちょっと甘い所があったりして、映像面には時々安っぽい感じが出てしまってるんでけすど、でも、『ショーン・オブ・ザ・デッド』を参考にしたと思しきストーリーの面白さや、ユニークな主人公のキャラクターなどでもって、映画の面白さが損なわれていないように作られているのは凄いです。中身がしっかりしてるんで、外面のB級感覚が、むしろ「味」みたいに思えてくるんですよね。
ただ、所々に、展開がスローに感じてしまう箇所が出てきたり、「その設定って、必要なの?」と思えるような所があったりして、やっぱり、全体的に、『スパイダー・パニック』ほどの面白さには達してないという印象ではありました。でも、その「無意味かと思っていた設定」が、実は伏線だった事が後に判明したりするのが侮れないところです。
あと、主人公のキャラクターはこの手の映画群の中でもかなり面白い部類でしたね。いわゆるダメ人間系統ではあるんですけど、何気に、勇気と行動力がそこそこありましたし、ユーモア感覚はかなりのものを持っていて、どのジャンルのパニック映画に出ても、ムードメーカーとして活躍しそうなポテンシャルの高さが感じられる奴なんです。
ただ、他の映画だと、間違いなく主役のポジションには来られないタイプのキャラではあるんですよね。それどころか、中盤頃で死んでもおかしくないぐらいの立場だと思います。で、そういうタイプのキャラが主役を張っているというのもまたこの映画の面白い点の一つでもあるんですよね。
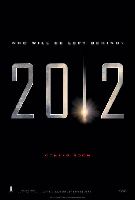 2012
2012
<2012>
個人的評価 49点 (50点満点中)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)
◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)
◎おススメ度 ★★★★☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)
◎大破壊度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)
 <個人的感想>
<個人的感想>
世界規模パニック映画の雄、ローランド・エメリッヒによる新作ディザスター・ムービーという事で、本来なら特大の期待を寄せていてもおかしくないところなのですが、何故か今回は不安も大きかったんですよね。
まず、『インデペンデンス・デイ』『デイ・アフター・トゥモロー』と、この手の映画の大傑作を2本もものにしてるだけに、もうそろそろこのレベルの映画は撮れないんじゃないかという懸念があったからでした。だって、一人の監督がそう何本も同ジャンルの傑作を撮るなんて難しいでしょうからね。
そしてもう一点ですが、最初にこの映画の予告編を見た時、その大スペクタクルシーンの映像に対して、何の驚きも無かったんですよね。多分、『デイ・アフター・トゥモロー』の頃に見たら「これは凄ぇ!」と唸る事になったと思いますが、あれから5年。VFX技術もさらに進歩して、こういう、大規模な破壊シーンが出てくる映画というのも何本か出てきました。そういう映画を見続けてきた事で、もう、ちょっとやそっとの「凄い映像」では驚けない体になってしまってるわけですよ。
ですが、真に「大作映画を任せられる監督」というのは、ただ派手な映像を垂れ流してくるだけではなく、その凄い映像を「いかに凄いように見せるか」というのにもこだわってくるものです。
そして、この映画の監督エメリッヒこそ、そういう、「大作映画を安心して任せられる監督」の一人なわけですよ。それを、今作を見て改めて思い知らされる事となりましたねぇ。
予告では、ただ単に凄い事が起こっている場面を見せてるだけとしか思えなかった一連のディザスターシーンですが、本編を見てみたら、「こ、こんな凄い映像、見た事ねぇ!!」と驚愕する事になってしまいました。
いやぁ、もう、さすがエメリッヒと言うしかないですね。去年の年末に、やたら物足りない都市崩壊描写が出てきた映画がありましたけど、あの映画に足りなかったものが全て詰まってましたからね。「これこそ、年末公開の大作映画だ!」と感動するぐらいでした。
では、具体的に何が凄かったのかと言いますと、まず、これまでの監督作で出てきた災害シーンと同様、「その災害に今まさに巻き込まれている人」の描写をしっかり入れてきている事。都市崩壊の全景だけではなく、人間目線からのシーンが入る事で、その災害の凄さをリアルに想像する事が出来るんですよね。
そして、予告で見ていた通り「過去最大級の都市破壊描写」が出てくるわけですが、今回、その過去最大級の都市破壊の真っ只中に、主人公がいるという設定をぶっこんできてるんですよね。しかも、その最大級の都市崩壊地区の中を、主人公が車や飛行機で駆け抜けるんです。
倒壊してくる建物やら地割れやら隆起してくる地面やら、もう、ありとあらゆるものがドッカンドッカン迫ってきて行く手を阻んでくるんですよ。とあるシーンでは、「こんなものが行く手を遮る障害物になり得るなんて!」と驚かずにはいられないようなものが吹っ飛んできてましたからねぇ。
で、主人公達の乗った車なり飛行機なりでもって、そういった、ありとあらゆるものが吹っ飛んでくるのを回避しながら突き進んで行くんですよ。
これは凄い。いや、驚きましたね。こんな映像見た事ないです。VFXの技術的なものには、特に素人目に見て斬新みたいな面は無かったんですけど、VFXの使い方に関するアイデア面は間違いなく斬新でした。
ここまで来ると、もう、映画と言うよりも、ゲームの世界に近いみたいな感じになっていて、リアリティはかなり薄くなってはいるんですよね。でも、そのおかげで、まるで、架空の都市の崩壊シミュレーションを見てるみたいな感じがあって、「この災害でどれだけの命が失われているのか」という面にあまり気が回らないようになってるんです。
世界のほとんどの人が死ぬ映画なのに、見ていて、『ダイハード2』の飛行機墜落シーンの半分も良心が痛まないぐらいなんですよね。そして、代わりに、人々の中に眠っている「大破壊を見たい」という欲求にのみ見事に応えてくれるわけですよ。
と、ディザスター描写は完璧だったんですけど、どうも、その後が続かなかったという印象で、後半はかなりの失速を感じてしまいました。と言うか、この人の映画は大抵、前半1時間のテンションが最後まで持たないんですよね。中だるみをするか、尻すぼみになるかのどっちかで。
個人的には『デイ・アフター・トゥモロー』は後半のドラマも面白く見られたんで、「エメリッヒ監督作の中で、唯一、ダレる箇所が無かった映画」という位置付けだったんですけど、一般的にはこれも尻すぼみ系の映画ですよね。で、今回の『2012』もおんなじような流れになっていたんですけど、今回は私も後半のドラマにはあんまりノレなかったんですよね。
冗談抜きで、私はエメリッヒは「割りとドラマをしっかり語ってくる系の監督」と思っていまして、毎回、人間ドラマ面にもそれなりの面白味を感じていました。今回だって、いい場面もあったと思いましたし。でも、最終的には「煮え切らない」という印象で終わってしまった感がありましたねぇ。
あと、何か余計なシーンが多かったような気がしたんですよね。クライマックスのゴタゴタって、無くても良かったんじゃないだろうか。あるいは、もっと別の見せ方にするとか。何か、一瞬、邦画のパニック映画を見てるのかと思ってしまうぐらいの「安っぽさ」がドラマシーンから出てしまってるように感じられてしまいました(なんて言いながら、邦画のパニック映画なんて見た事ないんで、話に聞くイメージでの話なんですけどね)。
(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください
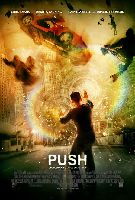 PUSH 光と闇の能力者
PUSH 光と闇の能力者
<PUSH>
個人的評価 35点 (50点満点中)
◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)
◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)
◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)
◎ダコたん度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)
 <個人的感想>
<個人的感想>
見る前は、『HEROES』みたいな、スーパーパワーを持った連中が出てくるヒーロー物のストーリーなのかと思ってたんですけど、どちらかと言うと、「超能力物」という雰囲気の映画だったんですね。
例えば、『HEROES』なんかは、視覚的に派手だったり攻撃的だったりする能力を持ってる連中がいるのにも関わらず、テレビシリーズで制作費が少ないせいか、アクションシーンがあんまり出てこないんですよね。それがちょっと残念だったりしたんですけど、この映画の場合、元々出てくる能力というのが、視覚的に地味なのが多いんで、「アクションシーンが少ない」という点にガッカリ感が無いんです。だから、純粋に、ストーリー面に興味が向くんですよね。
で、そのストーリーですけど、何か、変に複雑でこんがらがった話だったような感じで、だいたいの流れみたいなのは分かったものの、細かい部分はかなり意味不明でスルーしてしまった所があったりしました。
元々複雑な脚本だったのか、私の頭がおかしいのかどっちか分かりませんが(多分、後者なんだろうな・笑)、例えば、今ストーリーがどこに向かおうとしてるのかとか、この人が何を目的として行動しているのかが分からなくなる時があったんです。
そんな事になってしまった原因として、「この物語特有の専門用語が色々と出てくる」「各人物が何の能力を持っているのか分かりづらい(『X−MEN』とかと違って、パッと見て分からない場合が多い)」「未来を予測する能力や、人に嘘の記憶を植え付ける能力が絡んでくるせいで、ストーリー展開やキャラの行動があっち行ったりこっち行ったりする」といったのがあると思います。
とは言え、まあ、大まかな流れだとか、ストーリーを楽しめる最低限の所は私でもついて行けたんで、「意味が分からなくて、つまらん」という思いが出なかったのは幸いでした。
要するに、主人公側と敵側とで、ある物の争奪戦を繰り広げるというお話で、「こちらがどう行動するのか」というのが、敵側の「未来予知」の能力者によって予測されてしまう、というサスペンスがあるのは面白かったと思います。
主人公側にも未来予知の能力者はいるんで、それで後の行動を考えたり、敵の裏をかいたりといった、駆け引き的な要素が出てくるわけですよ。まあ、この能力のせいで話がややこしくなってるという面もあるんですけど、これはこれで面白くて良かったとは思います。
で、この主人公側の未来予知能力者を演じるのがダコたんで(何だ、その呼び名・笑)、いわゆるヒロイン的立場なわけなんですけど、実はもう一人ヒロインがいるんですよね。
と言うか、こっちの方が「第一ヒロイン」になるんでしょうかね。主人公とのロマンスがあったりしますし、ストーリーのカギを握るキャラクターですし。で、こっちを演じてるのがカミーラ・ベルという、その昔、『沈黙の陰謀』で、セガールの娘役をやってた人なんですよね。
要するに、「元セガールの娘」と「元トム・クルーズの娘(ショーン・ペンの娘だった時もあり)」が共演してるわけですよ。何だか、豪華な感じがするキャスティングですねぇ。
(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください
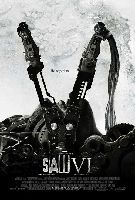 ソウ6
ソウ6
<SAW VI>
個人的評価 28点 (50点満点中)
◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)
◎評価度 ★★☆☆☆ (客観的に評価してみる)
◎おススメ度 ★☆☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)
◎継続は力度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)
 <個人的感想>
<個人的感想>
早くも6作目となった『ソウ』シリーズ。あっと言う間に『ロッキー』『ハリー・ポッター』シリーズに並んでしまいましたね。何しろ、年1本のペースですからねぇ。ここ数年は、秋になったら「あ、そろそろ『ソウ』の季節だな」とか思うようになってきましたし、もう“ソウ”という言葉を秋の季語にしてもいいんじゃないかと思うぐらいです。
で、それだけ早いペースで続編が作られてると言う事で、もう、一作毎に独自の色を出したりとか、「作り込み」をしてる暇が無いわけですよ。ただひたすら、1作目のエッセンスを絞り取る事のみに力が注がれているようなものなんですけど、もう最近作では、この「絞り込み」が見所と化してる感がありましたからね。
この「いかに強引に話を続けていくか」という辺りの製作側の苦心が垣間見えるようで、段々とこのシリーズを応援していきたいという気になってきました。当初は残酷なだけで面白くないという印象の、あまり好きじゃなかったシリーズだったんですけど、今や「今度はどんな強引な引き伸ばしをしてくるんだろう」というのが楽しみでしょうがないです。
でも、それでも残酷映画としての最低限のクオリティは毎回保たれていて、それなりに見応えはあったりするのが侮れない所です。
ジグソウの仕掛ける残酷ゲームの場面が毎回見所になってるわけですけど、「よくこんなの考えるな」と思うようなアイデアの詰まった残酷ゲームと残酷な死に様が毎作出てきて、この点に関しては手抜かりが無いんですよね(ストーリーはもう無理繰り感ありまくりな状況になってるんですけど・笑)。
こういう、押さえるべき点をしっかり押さえられているからこそ、ここまでシリーズが続けられているんでしょうね。
ちなみに、今回、全く新味が無いというわけではなく、「社会派な面を出してみる」という新機軸があったのには笑いましたね(笑う?)。
具体的に言うと、マイケル・ムーアの『シッコ』でも描かれた、アメリカの悪質な保険会社の実態にメスが入れられてるんです。「人の命を救わない事で金を儲けている」という保険システムに、我等がジグソウが怒りの鉄槌を下すわけですよ。何か、ちょっと溜飲が下がる感もあったりしましたね、今回(笑)。
こういう感じで、「日頃、腹が立つなと思っている連中」に対して、ジグソウがお仕置きをする、という流れは面白いかもしれませんね。あと2作ぐらいこの路線が続いてもいいかも(ジグソウはもうとっくに死んでるんですけど、きっと、ここはもはや気にしてはいけない点なんでしょう)。
そうだ、次回作は、「映画館で、上映中に延々ベラベラと喋ってる輩がジグソウ軍団にとっ捕まって、拷問ゲームをやらされる」という内容にするのはどうだろう。いや、今回見てる時、同じ劇場内にいたんですよね、そういう連中が(「命を粗末にしてる」とか関係無いから駄目かね)。
 ファイナル・デス・ゲーム
ファイナル・デス・ゲーム
<OPEN GRAVES>
個人的評価 27点 (50点満点中)
◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)
◎評価度 ★★☆☆☆ (客観的に評価してみる)
◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)
◎B級度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)
 <個人的感想>
<個人的感想>
「古代に作られた謎のボードゲームが出てきて、そのゲームに出てきた事が現実でも起こってしまう」という、今更ながらの『ジュマンジ』のバッタ物で、『ジュマンジ』に出ていたキルスティン・ダンストと『チアーズ』で共演していた、エリザ・ドゥシュクが出ていたりします。この人を見るの『トゥルー・コーリング』以来ですね。
さて。サイコロを2個振って、出た目の合計分コマを進ませるというのは『ジュマンジ』と一緒ですが、止まった所にあるのは「何も無い」か「死のカードを引く」の2つで、どちらかと言うと「死のカード」のマスの方が多いっぽい感じでした。
で、その「死のカード」を引くとどうなるのかと言うと、ゲームオーバーになるんです。カードの裏には「どうやって死ぬのか」というのが書いてあるんですが、かなり漠然とした文章なので、「カードに書かれた事が本当に起こる!」と分かっていても、何が原因で死ぬ事になるのかよく分からないぐらいです。
と、このように、かなりクソゲー臭の強いゲームなんですが、この不条理な難易度のゲームをもしクリアする事が出来れば、何と、どんな願いでも一つだけ叶えてもらえるのです。
だから、多分、本来は欲に駆られた人達がやるようなゲームなんでしょうね。でも、この映画でゲームをプレイする事になる若者達は、これが魔法のゲームだという事も知らず、ただのボードゲームだと思ってやり始める事になります。
登場人物が、「このゲームが魔法のゲームだと知ってて敢えて挑戦する」、という描き方もあったと思うんですけど、そこを「何も知らずにプレイし始めてしまう」という、『ジュマンジ』と同じ方式を採用したわけですよ。いやぁ、見事なチャレンジ精神です(まあ、色々考えた結果、この方式の方が面白いという事になったのでしょうね)。
ちなみに、主人公達の前にこのゲームをやっていた奴というのが出てくるんですけど、こちらは、どうやら「知ってて挑戦した」パターンだったみたいでしたね。
ゲームは完全にサイコロの運次第になるので、映画的には見てて面白いものではありません。なので、「犠牲者がどうやって死ぬのか」というのがメインの見せ場になってくるわけですが、一応、予言はされてるんですから、誰がどう死ぬのかなんて、予想出来そうだと思うじゃないですか。
でも、先にも書いたように、かなり漠然とした書かれ方をされてるうえ、「そもそも、誰がどんな予言を引き当てたか」なんて、こちらは覚えていられないので、「誰が、どう死ぬのか分からない」という状態で見ていく事になるんです。
これが、『ファイナル・デスティネーション』シリーズを連想させてちょっと楽しげなんですけど、やっぱり、あの映画ほど凝ってはいないんですよね。せっかく、ここまであからさまに『ジュマンジ』をパクったのなら、こっちの面ももっと堂々とパクって欲しかったところです。
ただ、中には呪いを受けたみたいな死に方をする人も出るんで、「死の“原因”」ではなく、「どういう死に様か」の方に力を入れたかったのかもしれないですけどね。
ちなみに、ゲームの詳しいルールというのはあまり深く語られてなくって、例えばズルをしたりだとか、一旦全員ゲームオーバーになった後、またすぐに2回目を始めたらどうなるのかなど、「もし現実にこういうゲームがあったら、やりそうだな」と思う所に何の説明も無いんですよね。
そもそも、ゲームオーバーになった人は、その場ですぐに死ぬわけではなく、後日、いつどこで何が原因で死ぬか分からないという状態になるので、下手したら、「ゲームオーバーを繰り返し、何時間か掛かってようやくクリアしたけど、それまでに死のカードを何枚も引いた」みたいな状況だって起こりうるわけです。
せっかく、以前このゲームをやったというキャラがいるんですから、そういうイカサマ対策のセリフを一つ加えてくれても良かったのにとか思ってしまいます。まあでも、きっと、イカサマをしたら何かよく無い事は起こるんでしょうな(そりゃ、「何でも願いが叶う」ぐらいの強力な魔力のかかった道具ですからね)。
と、脚本に穴が無いわけではないし、オリジナリティがあるわけでもない。ホラー映画としてのレベルも決して高くはない。という映画ですけど、重要なのは、『ジュマンジ』のバッタ物が作られたという事ですよ。こういう、ユニークなネタの映画は、こちらも「こういう映画をもっと見たい」と思うんですけど、やっぱり、A級映画だと中々作ってもらえないんですよね。色んな事情があって(多分、正統で真っ当な事情)。
そこを潜り抜けて、「あのネタをもう一度」みたいな映画をこうして作ってもらえるというのは、それなりに有り難い事だと思うんです。評論家やまともな映画ファンにとっては迷惑な話だとは思いますけど(笑)。
(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください
 スペル
スペル
<DRAG ME TO HELL>
総合評価 35点 (50点満点中)
◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)
◎肯定度 ★★☆☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)
◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)
◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)
◎お年寄りは大切に度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)
 <個人的感想>
<個人的感想>
ゴーストハウス・ピクチャーズの総師こと、サム・ライミが自らメガホンを取った映画であり、ホラーファンにとっては、出世作『死霊のはらわた』シリーズ以来となるホラー映画という事で話題の一作です。
もちろん、私も期待をしていたのですが、どうも、見ていて「いまいち、ノリきれない」という思いでした。と言うか、どう楽しんだらいいのか分からない感じなんですよね。
ホラー映画としての怖さもありながら、コミック風の派手な演出で笑えるところもある、という、『死霊のはらわた』と同じ雰囲気の作りだとは思うんですけど、「怖さ」と「笑い」が何かチグハグで、バランスが悪いように思えてしまったんです。
例えば、怖い事が何も起こらない普通のシーンや、怖い事が起こりそうな雰囲気を出してるシーンには“現実味”というのが存在してるんですけど、怖い事が起こる場面になると急にリアリティが無くなって、マンガっぽい演出が出てくるんですよね。どういう心持ちで映画を見ていればいいのか、混乱してしまいました。
多分、この映画の波長に合わせる事が出来れば、全てが上手くハマってるように感じられてくるんだと思うんですけどね。本来なら楽しいはずの「呪いババアの襲撃シーン」も、悪い意味でこちらの予想と違う、やり過ぎな攻撃を出してくるんで、戸惑ってしまうんです。
でも、終始そういう演出なんですから、途中から慣れてきてもいいはずですし、そもそも、オープニングの段階からして、「この映画はどういう雰囲気の映画なのか」というのをしっかり示してきているんですよね。だから私も分かっているつもりだったんですけど、何故か最後までこの映画の波長に合わせる事が出来ず終いでした。
実は、『ダークマン』を見た時も同様の戸惑いがあって、あんまり楽しめなかったんですよね。一瞬、「私はサム・ライミと相性が悪いんだろうか?」と思ってしまいましたけど、『スパイダーマン』シリーズはもちろん、『死霊のはらわた』シリーズも普通に好きなんで、相性の問題では無いんでしょう。
では、この映画に対する違和感は何なんだろうと考えてみて、一つ思い浮かんだのは、主演俳優の醸し出す空気が、映画の雰囲気に合ってないという事なのでは、というものでした。
主演のアリソン・ローマンはいい演技をしていると思うんですけど、いわゆる、普通のホラー映画のヒロインとリアクションとかテンションとかが変わらないんですよね。やっぱり、サム・ライミの演出って、ホラー映画としてもホラーコメディ映画としてもちょっと特殊だと思うんで、それに合った、特殊な個性を持ってる人が主演じゃないと(例えば、ブルース・キャンベルみたいな人ですね)、どこかでズレのようなものが感じられてしまうと思うんです。もしかしたら、『ダークマン』も同様の理由であまり楽しめなかったのかもしれません(『スパイダーマン』シリーズなんかは、ハリウッド大作という事で、アクを落としてる風の演出でしたから、そういうような事を感じなかったんでしょうね)。
でも、そのサム・ライミ本人は「この映画の主演はアリソン・ローマンで決まりだ」と思ってるからこそ抜擢されてるわけで、単に、私が考え違いをしてるだけなんでしょう。私だって、後に見返した際に、急に波長が合って、絶賛に鞍替えしないとも限りませんからね。
ただ、これは編集の問題なのかもしれないですけど、呪いの力による攻撃を受けて、物凄い痛がっていたその次のショットであんまり痛がってないみたいな、リアクションが変な時というのがちょくちょく出てきてたのは、「何なんだろう?」と思ってしまいました。こういうのを見ると、映画に、悪い意味での「うそ臭さ」が感じられてしまって、テンションがちょっと下がってしまいます。
という訳で、「現時点では、ちょっとノレない映画」という事になるんですが、見終わった後の印象は決して悪いものではありませんでした。と言うのも、ラストが実にいい締め方をされていたんですよね。予想通りのラストではあったんですけど、全てが終わった後、エンドクレジットの出る直前に、タイトルが「ドーン!」と出る所が、何か力強くてカッコイイなぁとか思ったものでした。
あと、元々、注目してる人だからというのもあると思うんですけど、主人公の相手役であるジャスティン・ロングもいい印象を残してました。演じるキャラクターも、今年見た映画の中でもトップクラス級のナイスガイで、実に爽やかでしたね。
そして何と言っても、後半の重要且つ深刻な場面で登場したヤギの存在感のデカさですよ。もう、思いっきり、場面をさらっていってましたからねぇ。「ヤギ、すげぇ!」とか思ったものでした。
深刻な顔の主人公と、超深刻な顔の霊媒師の間に、アホみたいに平和なツラでヤギが佇んでいるというショットは、もしあと数秒長く続いてたら、一人で声を上げて笑ってしまうところでしたよ。コイツにとってもヤバい状況だと言うのに(笑)。結局、この映画で一番印象に残ったのは、呪いババアよりも、このヤギの方でしたねぇ。
 ←前に戻る
←前に戻る THE 4TH KIND フォース・カインド
THE 4TH KIND フォース・カインド <個人的感想>
<個人的感想>
 <個人的感想>
<個人的感想>
 <個人的感想>
<個人的感想>
 <個人的感想>
<個人的感想>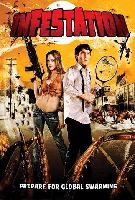
 <個人的感想>
<個人的感想>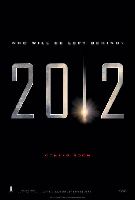
 <個人的感想>
<個人的感想>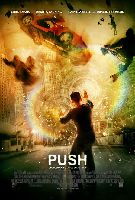
 <個人的感想>
<個人的感想>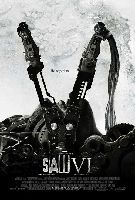
 <個人的感想>
<個人的感想>
 <個人的感想>
<個人的感想>
 <個人的感想>
<個人的感想> ←前に戻る
←前に戻る